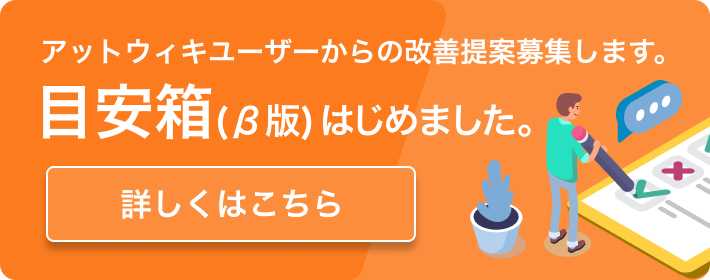2004年、京都――
春の陽気に包まれた街では、新時代の健やかな風が吹いていた。
道行けば趣深い木造の家屋が立ち並び、時おり色褪せた鳥居が顔を出す。
ひとたび山の方へと足を運べば千年時を巻き戻したかのような古風な街並みと、そこに群れる観光客の姿を窺うことができるであろう。
道行けば趣深い木造の家屋が立ち並び、時おり色褪せた鳥居が顔を出す。
ひとたび山の方へと足を運べば千年時を巻き戻したかのような古風な街並みと、そこに群れる観光客の姿を窺うことができるであろう。
変わらない過去と積み重ねた年月の重みが強調される一方で、だからこそだろう、新時代の臭いも漂っている。
いかにも“京都らしい”黒い格子の据えられた町屋が続いていた――かと思うと、一つ角を回った先にはぴかぴかとした看板を掲げたコンビニエンスストアと行き遭うこともある。
それだけでなく外国由来のファストフード店であったり、カフェだったり、当代風の建築物も当然のように街には存在する。
極め付けが京都駅で、全面ガラス張りの近未来的な外観に機能的な構造、様々な人種の人々が行きかうその様は過去を重んじる街並みとはどこか相容れない。
いかにも“京都らしい”黒い格子の据えられた町屋が続いていた――かと思うと、一つ角を回った先にはぴかぴかとした看板を掲げたコンビニエンスストアと行き遭うこともある。
それだけでなく外国由来のファストフード店であったり、カフェだったり、当代風の建築物も当然のように街には存在する。
極め付けが京都駅で、全面ガラス張りの近未来的な外観に機能的な構造、様々な人種の人々が行きかうその様は過去を重んじる街並みとはどこか相容れない。
そのことに賛否はあろうが、けれどもそのちぐはぐさというか、折り合いのつかなさというのが、逆にこの街特有の“臭い”を形作っているように思う。
過去を全面に出すことで、逆説的に未来を意識する。
未来が目につくことこそ、過去がそこにある証左である。
光強ければ影も――というようなロジックで、この街の現代(いま)という奴は生まれているのだ。
過去を全面に出すことで、逆説的に未来を意識する。
未来が目につくことこそ、過去がそこにある証左である。
光強ければ影も――というようなロジックで、この街の現代(いま)という奴は生まれているのだ。
と、少なくとも彼女、織作茜は感じていた。
「……一週間」
――その日、京都は、どこか蒸れた空気が漂っていた。
昨夜はひどく雨が降っていた。豪雨とまではいかないが、春雨、というには少し勢いのありすぎる、鋭く、冷たい雨が京都の街を濡らしていた。
朝を迎えた空は静まり返り、夜のことなど忘れたかのように澄み渡った快晴の空となったが、しかしそれで夜のことがなくなる訳がない。
風にざわめく木々はしっとりと濡れ、アスファルトには濁った水たまりができている。打ち捨てられたビニル傘が視界の隅を過った。
雨は――確かに降ったのだ。
たとえ昼では意識されずとも、夜の残滓は確かに街に残っている。
朝を迎えた空は静まり返り、夜のことなど忘れたかのように澄み渡った快晴の空となったが、しかしそれで夜のことがなくなる訳がない。
風にざわめく木々はしっとりと濡れ、アスファルトには濁った水たまりができている。打ち捨てられたビニル傘が視界の隅を過った。
雨は――確かに降ったのだ。
たとえ昼では意識されずとも、夜の残滓は確かに街に残っている。
「…………」
勢いよく流れゆく河を、じっ、と見つめながら茜はそう漏らした。その場は今出川通りの橋の下、鴨川と高野川がちょうど合流する地点であり、頭上では人が多く行きかっている。
そんな人通りから外れた、橋の下。石が乱雑に積み上がった河原で、茜は今しがた唱えた言葉を反芻した。
一週間。
その期間が意味することは――一つしかない。
そんな人通りから外れた、橋の下。石が乱雑に積み上がった河原で、茜は今しがた唱えた言葉を反芻した。
一週間。
その期間が意味することは――一つしかない。
「……そうですね。もうそのくらいになるんでしょうか」
隣で、声がした。
少女であった。透き通るような白い肌をした、小柄で、どこか儚い印象を与える可憐な少女。
薄紅色の和装を身に纏う彼女は、現代では少々異物であるようにも思えるが、京都の街の“過去”の部分にはこの上なく溶け込んでいた。
彼女は、茜がぽつりと漏らした言葉を拾い上げるように、
少女であった。透き通るような白い肌をした、小柄で、どこか儚い印象を与える可憐な少女。
薄紅色の和装を身に纏う彼女は、現代では少々異物であるようにも思えるが、京都の街の“過去”の部分にはこの上なく溶け込んでいた。
彼女は、茜がぽつりと漏らした言葉を拾い上げるように、
「――聖杯戦争が始まってから」
そう言った。
――その日、その時代の京都では、とある儀式が行われていた。
この世には、時代にそぐわぬ神秘と呼ばれる概念がある。
根源。この世を貫くありとあらゆる事象の出発点。渦巻く起点より分かたれた幾多もの支流。
未だ表層に希釈されず――一般まで届かぬ魔の流れこそ、神秘であり、それを追い求める者を魔術師と呼ぶ。
本来それは、茜とは何の縁もない世界のはずだった。茜は魔術師などではない。根源など知らぬし、求めてもいない。
そんな訳の分からないものに関わることになるとは、ついぞ思わなかった。
根源。この世を貫くありとあらゆる事象の出発点。渦巻く起点より分かたれた幾多もの支流。
未だ表層に希釈されず――一般まで届かぬ魔の流れこそ、神秘であり、それを追い求める者を魔術師と呼ぶ。
本来それは、茜とは何の縁もない世界のはずだった。茜は魔術師などではない。根源など知らぬし、求めてもいない。
そんな訳の分からないものに関わることになるとは、ついぞ思わなかった。
――しかし
何の因果か、茜はこの場にいる。
聖杯戦争なる魔術師の儀式に、彼女は参列することとなった。
聖杯戦争なる魔術師の儀式に、彼女は参列することとなった。
「……あの人は」
薄紅色の少女は回想するように述べる。色素の薄い髪が風に吹かれはためいた。
「あの人は結局、あの場で――死んだのでしょうか」
――死んだ。
その言葉を聞いた時、茜は自分を取り巻く世界が蜃気楼のように揺らいだように思えた。
降りつける雨、駆け抜ける刃のきらめき、嗤う鬼の面、そして流れゆく鮮血――過去が、昨夜の記憶がフラッシュバックする。
降りつける雨、駆け抜ける刃のきらめき、嗤う鬼の面、そして流れゆく鮮血――過去が、昨夜の記憶がフラッシュバックする。
――聖杯戦争とはつまるところ、殺し合いである。
魔術は知らぬ。理解もできぬ。根源など興味もない。けれども――その事実は他の何よりも分かりやすかった。
聖杯戦争――それは魔術師の闘争である。人類が築いてきた過去を、現代のモノとして語り、呼び寄せ、ありとあらゆる未来を綴る願望器を得る――殺し合い。
剣士、槍兵、弓兵、騎乗兵、魔術師、暗殺者、狂戦士、あるいは異聞の階位に過去の英霊を当てはめ、顕現させ、使役させる。
聖杯戦争――それは魔術師の闘争である。人類が築いてきた過去を、現代のモノとして語り、呼び寄せ、ありとあらゆる未来を綴る願望器を得る――殺し合い。
剣士、槍兵、弓兵、騎乗兵、魔術師、暗殺者、狂戦士、あるいは異聞の階位に過去の英霊を当てはめ、顕現させ、使役させる。
――呼びつけた英霊を指さして僕(サーヴァント)とは、恐れ多くもよく言ったものだ。
少なくとも、茜は気後れする。自らの願望のために、名のある英霊に主人と僕の関係を迫るなど。
――しかし何の因果か、茜はここにいる。
「セイバー」
茜は、己がサーヴァントをそう呼びつけた。
そう隣にいる少女こそ、セイバー――剣士の階位を据えられた英霊なのである。
彼女と共に、茜はこの一週間聖杯戦争に臨み、そして――
そう隣にいる少女こそ、セイバー――剣士の階位を据えられた英霊なのである。
彼女と共に、茜はこの一週間聖杯戦争に臨み、そして――
――殺した。
昨夜、雨の中にあって彼女は殺し合った。
21世紀の京の都にて現界せし英霊たち。彼らは運命づけられたように殺し合い、そして散っていった。
21世紀の京の都にて現界せし英霊たち。彼らは運命づけられたように殺し合い、そして散っていった。
――雨が、降ったのだ。
昨夜、京都では雨が降っていた。
あの雨の中、京都は一層濃い闇が広がっていた。
あの雨の中、京都は一層濃い闇が広がっていた。
「あとどれだけの時間、どれだけの人が、この京に――」
――囚われるのか。
濁った鴨川の流れを見つめつつ、茜はぽつりと漏らした。
彼女はこの聖杯戦争の全容を未だ把握していなかった。
元より魔術など何も知らぬ身であるから当然ではあるのだが――しかしそもそも何騎の英霊が召喚されているのかさえ、さだかではなかった。
あの軽薄な進行役は、その程度のことさえ教えてくれなかった。盤上を俯瞰することは、今の茜には許されてはいない。
濁った鴨川の流れを見つめつつ、茜はぽつりと漏らした。
彼女はこの聖杯戦争の全容を未だ把握していなかった。
元より魔術など何も知らぬ身であるから当然ではあるのだが――しかしそもそも何騎の英霊が召喚されているのかさえ、さだかではなかった。
あの軽薄な進行役は、その程度のことさえ教えてくれなかった。盤上を俯瞰することは、今の茜には許されてはいない。
それ故に、これまでの戦歴から大体の様相を掴むしかない
―― 一騎目は鬼面のバーサーカー。
初日に光縁寺で遭遇して以来、既に数度戦っている因縁深い相手である。
狂うておる筈なのに、しかし彼は鬼面越しに綽綽と喋り、その剣技も冴え渡っていた。
彼はきっとまだ生きているだろう。あの雨の祇園にて、姿を見失ったが……
狂うておる筈なのに、しかし彼は鬼面越しに綽綽と喋り、その剣技も冴え渡っていた。
彼はきっとまだ生きているだろう。あの雨の祇園にて、姿を見失ったが……
――次に、三日目に遭遇したキャスター。
彼についてはしかめっ面の僧侶、という以上情報がほとんどない。接触の途中でバーサーカーの乱入を受けたためだ。
どちらかというとマスターの方の印象が強かった。あの気丈で飄々とした女性は、茜の知る婦(おんな)とは異なるものだった。キャスターの方は二輪車の隣でふて腐れていただけだ。
彼らとはそれっきり遭遇していない。その為、今現在も生き残っているかは謎だった。
どちらかというとマスターの方の印象が強かった。あの気丈で飄々とした女性は、茜の知る婦(おんな)とは異なるものだった。キャスターの方は二輪車の隣でふて腐れていただけだ。
彼らとはそれっきり遭遇していない。その為、今現在も生き残っているかは謎だった。
――そして、昨夜の乱戦にて顔を合わせることになったランサーとライダー
昨夜の戦いで、セイバーと刃を交わした者たちだった。
それにバーサーカーを交え、四騎のサーヴァントたちが雨の祇園を駆け抜けたのだった。
それにバーサーカーを交え、四騎のサーヴァントたちが雨の祇園を駆け抜けたのだった。
以上の四騎が、茜がこれまでに遭遇した陣営であった。
それに――セイバーを入れて五騎か。
あの進行役が言うには、この儀式の基準となった聖杯戦争は七騎で行うものであるらしかった。
で、あるならば既に過半数のサーヴァントとは接触できたことになる。
それに――セイバーを入れて五騎か。
あの進行役が言うには、この儀式の基準となった聖杯戦争は七騎で行うものであるらしかった。
で、あるならば既に過半数のサーヴァントとは接触できたことになる。
――とはいえ。
茜はあの進行役の注釈を思い出す。
この聖杯戦争においては、その限りではないかもしれない、と。
そうであるならば、もしかすると七騎より多いかもしれない。逆に少ないかもしれない。
ここまで一切遭遇しなかったアーチャーとアサシンはそもそも存在しない、ということもあり得る。
この聖杯戦争においては、その限りではないかもしれない、と。
そうであるならば、もしかすると七騎より多いかもしれない。逆に少ないかもしれない。
ここまで一切遭遇しなかったアーチャーとアサシンはそもそも存在しない、ということもあり得る。
――巫山戯た話だ。
進行役、を名乗っていた男のぬらりひょんのような顔を思い出し、茜は不快そうに顔をしかめる。
「……色々ありましたけれど、私は京が好きです」
その顔をどう思ったのか、セイバーがふとそんなことを切り出した。
「土方さんなどは“土が赤すぎる。もっと黒い方がいい”とか難癖つけてましたけど。あは、全くあの人は――」
とりとめのない思い出を語るその横顔は――どこか寂しさを感じさせた。
無理もあるまい。剣士の英霊として顕現せし彼女の真名は沖田総司。
壬生狼――である。
新撰組、の旗の下、流れゆく時代の変節を直に駆け抜けた天才剣士。
無理もあるまい。剣士の英霊として顕現せし彼女の真名は沖田総司。
壬生狼――である。
新撰組、の旗の下、流れゆく時代の変節を直に駆け抜けた天才剣士。
かの英霊にとって、この京都こそまさに活躍した舞台である。
後世になって幾多の創作で歪められた点もあろうが――しかし、かの天才剣士がかつてこの都にいたということは、紛れもない事実なのである。
彼女は――多くの者と出会い、多くの者と別れ、そして何より多く者を斬り捨てた。
後世になって幾多の創作で歪められた点もあろうが――しかし、かの天才剣士がかつてこの都にいたということは、紛れもない事実なのである。
彼女は――多くの者と出会い、多くの者と別れ、そして何より多く者を斬り捨てた。
「あの人たちが今の京都を見たらなんて言うんでしょう……」
彼女が生きた時代から数える二世紀半。
現代――とされているこの時で、京の街では新世紀の風が吹いていた。
湿り気を含んだ風の中、桜色の剣士は一体何を想っているのであろうか――
現代――とされているこの時で、京の街では新世紀の風が吹いていた。
湿り気を含んだ風の中、桜色の剣士は一体何を想っているのであろうか――
◇
その昔――
京都で鴨川が増水し、西賀茂の浮田の森にあった神木が流れ出たことがあったという。
その神木はどんぶらこと川の流れに乗り、そしててんで別のところに行き着いた。
漂着した神木を見つけた当時の住民はこれ吉兆とありがたり、わざわざ社殿を造って祀ったのだとか。
その神木はどんぶらこと川の流れに乗り、そしててんで別のところに行き着いた。
漂着した神木を見つけた当時の住民はこれ吉兆とありがたり、わざわざ社殿を造って祀ったのだとか。
そうしてできたのが――賀茂別雷神社の境内末社にあたる半木神社であった。
「半木」と書いて「ながれぎ」と読ませるのは、この由来に依るものではないかとまことしやかに語られている。
「流木」が「半木」になったのだというが、見ればなるほど、河に面したその立地は何か木でも流れ着きそうではあった。
「半木」と書いて「ながれぎ」と読ませるのは、この由来に依るものではないかとまことしやかに語られている。
「流木」が「半木」になったのだというが、見ればなるほど、河に面したその立地は何か木でも流れ着きそうではあった。
と、まぁこの由来の真偽自体はどうでもいいことではあった。
21世紀の現在でもこの半木神社は変わらず鎮座しているが、この地にはもう二つ名所ができていた。
一つは京都府立植物園。そしてもう一つが――
21世紀の現在でもこの半木神社は変わらず鎮座しているが、この地にはもう二つ名所ができていた。
一つは京都府立植物園。そしてもう一つが――
「――桜、ですね」
茜はぽつりと漏らした。
見上げればそこで――桜が舞っていた。見渡す限り続く続く桜花のトンネル。
葵橋から御薗橋までの約二キロにも及ぶこの道こそ――半木(ながれぎ)の道であった。
見上げればそこで――桜が舞っていた。見渡す限り続く続く桜花のトンネル。
葵橋から御薗橋までの約二キロにも及ぶこの道こそ――半木(ながれぎ)の道であった。
「……色々と、変わりましたね。この辺りも……」
舞い散るソメイヨシノのただ中を、茜はセイバーと共に歩んでいく。
この桜の道ができたのは今から半世紀ほど前だという。なるほど、セイバーからすればこれもまた新時代の風、ということなのか。
この桜の道ができたのは今から半世紀ほど前だという。なるほど、セイバーからすればこれもまた新時代の風、ということなのか。
共に歩んでいると、目の前を幾人かの子供が通り過ぎて行った。
きゃっきゃっと甲高い声を上げながら川べりを走り回る彼らを眺めながら、茜は今後のことを考える。
きゃっきゃっと甲高い声を上げながら川べりを走り回る彼らを眺めながら、茜は今後のことを考える。
――方針はないに等しい。
この聖杯戦争において、茜はこれまで流されるように生きてきた。
積極的に動くことをよしとせず、さりとて死を選ぶような真似もせず――ただ生きてきたと言える。
積極的に動くことをよしとせず、さりとて死を選ぶような真似もせず――ただ生きてきたと言える。
己の願いもなく、それを支える個もありはしない。
聖杯戦争なるシステムと、それにより構築された網状組織(ネットワーク)の中、ぽつんと立っている。
それが今までの彼女の立場であった。
とはいえ――そろそろそれも改めなければなるまい。
聖杯戦争なるシステムと、それにより構築された網状組織(ネットワーク)の中、ぽつんと立っている。
それが今までの彼女の立場であった。
とはいえ――そろそろそれも改めなければなるまい。
「思ったよりも、人が少ないのですね」
辺りを見ながら茜はぽつりと漏らした。
シーズンを少し外れた平日とはいえ、未だ桜が咲き誇る季節だ。
本来ならば花見客がもっといてもおかしくない。
シーズンを少し外れた平日とはいえ、未だ桜が咲き誇る季節だ。
本来ならば花見客がもっといてもおかしくない。
……やはり、人々は感じているのだろう。
京都の風に混じる、暗く濁った血の色を。
京都の風に混じる、暗く濁った血の色を。
――今日この日、京都では既に不可解な事件が起きていた。
糺ノ森での狸騒動、“ホルモー”なる言葉をつぶやく謎の学生集団、賀茂大橋での蛾の大量発生――などという滑稽で、しかし奇妙な事件から数週間前より続く連続殺人事件のような如実に恐ろしいものもある。
そうした奇怪な、理解できない出来事の積み重ねが、人々の間に不安を生むのだろう。
何か――おかしなことが起きている、と。
その全てが聖杯戦争に関わっている訳ではないだろうが、しかし裏で実際に何かが起きているのは事実なのだ。
開幕から既に一週間が経った今、その波及を敏感に人は感じ取っているのだろう。
昨夜起こった祇園での乱戦など、明確に騒ぎになった事柄さえもあるのだから。
そうした奇怪な、理解できない出来事の積み重ねが、人々の間に不安を生むのだろう。
何か――おかしなことが起きている、と。
その全てが聖杯戦争に関わっている訳ではないだろうが、しかし裏で実際に何かが起きているのは事実なのだ。
開幕から既に一週間が経った今、その波及を敏感に人は感じ取っているのだろう。
昨夜起こった祇園での乱戦など、明確に騒ぎになった事柄さえもあるのだから。
「あ」と茜は思わず声を出す。不注意で水たまりを踏んでしまっていた。
この京都に来て新しく買った靴に泥が着いてしまっていた。
この京都に来て新しく買った靴に泥が着いてしまっていた。
「大丈夫ですか、マスター」
すると心配そうにセイバーが覗き込んでくる。
髪が、はらりと舞う。
「大丈夫」と答え泥を落としつつも、茜は今一度彼女の姿を見た。
髪が、はらりと舞う。
「大丈夫」と答え泥を落としつつも、茜は今一度彼女の姿を見た。
新たに洋装を用意した茜とは対照的に、セイバーは和装を身に着けていた。
薄紅色の和装とそのブーツは、彼女いたっての要望で用意したものだ。
この聖杯戦争にて、初めて行ったことは服の買い物、であったのだから。
薄紅色の和装とそのブーツは、彼女いたっての要望で用意したものだ。
この聖杯戦争にて、初めて行ったことは服の買い物、であったのだから。
はらはらと舞う桜の下に佇む、和装の少女。
その姿は儚く、けれども芯の通った凛々しさを湛えていて――
その姿は儚く、けれども芯の通った凛々しさを湛えていて――
「うん? どうかしましたか、マスター」
――茜の視線にセイバーが顔を傾げていた。
「あ、いや何でもありません。そのちょっと――」
――なんだ。
自分は今、彼女を見て一体何を思った。
自らの心の奥底で、ちら、と顔を見せた奇妙な感情の正体を探ろうとしたが。
自らの心の奥底で、ちら、と顔を見せた奇妙な感情の正体を探ろうとしたが。
「ぼうっとしてしまって……」
――違う。
そんなことではない筈だ。
今、自分はセイバーを見て、明確に何か――厭な想いを抱いた筈だ。
今、自分はセイバーを見て、明確に何か――厭な想いを抱いた筈だ。
「大丈夫ですか?」
セイバーは、茜のそんな煩悶を知ることなく、心配そうにそう尋ねてくる。
結果――茜は曖昧に笑ってしまう。誤魔化すために、かつて貼り付けていた婦(おんな)の笑みを。
結果――茜は曖昧に笑ってしまう。誤魔化すために、かつて貼り付けていた婦(おんな)の笑みを。
「ちょっとその辺りの茶屋で休みますか?」
「それもいいですね」
「あ! あそこでアイスクリーム売ってますよ。抹茶ですよ、抹茶」
「それもいいですね」
「あ! あそこでアイスクリーム売ってますよ。抹茶ですよ、抹茶」
その笑みを信じてか、セイバーは和装をはためかせながら氷菓子を買いにいった。
屈託ない笑みを浮かべ道を行くその姿は、絵に書いたような可憐な少女であり、とても人斬りには見えなかった。
その姿を見ている限りは、茜は何も思わない。先ほど感じたような、厭な想いは、何も――
屈託ない笑みを浮かべ道を行くその姿は、絵に書いたような可憐な少女であり、とても人斬りには見えなかった。
その姿を見ている限りは、茜は何も思わない。先ほど感じたような、厭な想いは、何も――
◇
それからしばらく休みを取り、また再び半木の道を散策しようとしていた時だった。
「……マスター」
辺りでは変わらず桜が舞っている。
隣で流れる河の流れがごうごうと響く中、湿り気の含んだ風が頬を撫でていく。
その中で――前を行くセイバーはふと足を止めていた。
そして、顔だけを茜の方へと向け、ふっと微笑んだのち、
隣で流れる河の流れがごうごうと響く中、湿り気の含んだ風が頬を撫でていく。
その中で――前を行くセイバーはふと足を止めていた。
そして、顔だけを茜の方へと向け、ふっと微笑んだのち、
「少々、待っていてください」
彼女は――ゆっくりと歩き出した。
茜を置いて、桜が降り注ぐ道を一人行く。
その先には―― 一人の少女が佇んでいた。
茜を置いて、桜が降り注ぐ道を一人行く。
その先には―― 一人の少女が佇んでいた。
「――――」
思わず茜は息を呑んだ。
セイバーと少女の風体が、あまりにも酷似していたからだ。
セイバーと少女の風体が、あまりにも酷似していたからだ。
花の文様が描かれた一斤染めの単衣。
色鮮やかな紅色を湛えた袴。
加えて流れるような黒髪に真っ赤なリボン。
そんな、如何にも少女然とした恰好とは裏腹に、その瞳は毅然と前を向き、可憐であると同時に凛々しい色を湛えている。
そして――その腰には一振りの日本刀が差してあった。
色鮮やかな紅色を湛えた袴。
加えて流れるような黒髪に真っ赤なリボン。
そんな、如何にも少女然とした恰好とは裏腹に、その瞳は毅然と前を向き、可憐であると同時に凛々しい色を湛えている。
そして――その腰には一振りの日本刀が差してあった。
ああ何と――似ていることか。
その衣装、そのありよう、その眼差し……二人の少女剣士は、全てが全て――鏡写しのようであった。
その衣装、そのありよう、その眼差し……二人の少女剣士は、全てが全て――鏡写しのようであった。
「サーヴァント――」
思わず茜は声を漏らす。
そう――突如現れた彼女もまた、英霊であった。
この京都にて行われた聖杯戦争にて召喚されたサーヴァントが一騎。
それらの情報を、茜はマスターとして読み取る。
そう――突如現れた彼女もまた、英霊であった。
この京都にて行われた聖杯戦争にて召喚されたサーヴァントが一騎。
それらの情報を、茜はマスターとして読み取る。
「マスター」
セイバーが呼びかけてくる。その糸を察し、茜は答えた。
「――セイバーでした」
それもまた――同じであった。
基本となるクラスは七騎であると教えられたが――なるほど、重複しないとはあの進行役も言わなかった。
基本となるクラスは七騎であると教えられたが――なるほど、重複しないとはあの進行役も言わなかった。
「そう、ですか」
セイバーは小さく頷く。そのやり取りの中でも現れたもう一騎のセイバーから視線は一切逸らしていない。
「――始めまして」
もう一人のセイバーは、まずはそう挨拶を口にした。
たおやかに、透き通る声で――
たおやかに、透き通る声で――
「もう気づいているでしょうけれど、私もサーヴァントです。
貴方たちのことは、昨夜、祇園の戦いで見かけました」
貴方たちのことは、昨夜、祇園の戦いで見かけました」
――やはり、か。
もう一人のセイバーの言葉に、茜は内心そう漏らす。
昨夜、あの雨の中自分たちは四騎のサーヴァントを確認した訳だが、乱戦の全容まで把握していた訳ではない。
ならばこそ、あの戦いにて一切接触できず観測できなかった者――あるいは一方的にこちらを観測した者がいてもおかしくはない。
そのことを予想していただけに、こうして次の日に接触してくることもまた、想定の範囲内ではあった。
昨夜、あの雨の中自分たちは四騎のサーヴァントを確認した訳だが、乱戦の全容まで把握していた訳ではない。
ならばこそ、あの戦いにて一切接触できず観測できなかった者――あるいは一方的にこちらを観測した者がいてもおかしくはない。
そのことを予想していただけに、こうして次の日に接触してくることもまた、想定の範囲内ではあった。
「それで」
セイバー、沖田は短く問う。
それで――貴方は何をしにきたのか、と。
そこに一切の遊びの色はなかった。律儀に挨拶をしてきた相手を迎えることもせず、その声色は刃のように鋭かった。
それで――貴方は何をしにきたのか、と。
そこに一切の遊びの色はなかった。律儀に挨拶をしてきた相手を迎えることもせず、その声色は刃のように鋭かった。
「一言で言います――同盟の提案です」
単刀直入な物言いに合わせ、もう一人のセイバーがそう切り出した。
「同盟?」と思わずセイバーは声を漏らす。
「同盟?」と思わずセイバーは声を漏らす。
「はい――同盟です。
この聖杯戦争は昨夜の戦いを持って状況が変わりました。
ランサーが倒れ、アサシンはバーサーカーと手を結んだ。加えて無軌道な動きを続ける殺人鬼と吸血鬼までいます」
この聖杯戦争は昨夜の戦いを持って状況が変わりました。
ランサーが倒れ、アサシンはバーサーカーと手を結んだ。加えて無軌道な動きを続ける殺人鬼と吸血鬼までいます」
茜が知り得ていない情報をさらりと彼女は漏らす。
一方的にこちらのことを知っていた事実と言う、どうやら彼女の陣営は情報を集めることが得手なようだった。
一方的にこちらのことを知っていた事実と言う、どうやら彼女の陣営は情報を集めることが得手なようだった。
「だから私たちと手を結びたいと? 聖杯を得るために――」
「いいえ、違います」
「いいえ、違います」
もう一人のセイバーはそう言って首を横に振った。
「私のマスターは彼らを止めたいと思っています。
そして、この儀式――聖杯戦争を破壊する心積もりです」
そして、この儀式――聖杯戦争を破壊する心積もりです」
彼女は迷わずに言った。
「それが私たちの――正義です」
――正義。
ああそれは何と、確固とした言葉だろう。
己の個の形成で悩む者にとって、その言葉はあまりにも強い過ぎる――
ああそれは何と、確固とした言葉だろう。
己の個の形成で悩む者にとって、その言葉はあまりにも強い過ぎる――
――正義とは何だろう。
だなんて、きっと目の前の少女は煩悶しないのだろう。
かつて悩んだのだとしても、己を納得し得るだけの答えは既に出し終えているに違いない。
かつて悩んだのだとしても、己を納得し得るだけの答えは既に出し終えているに違いない。
「……正義の味方、ですか」
対する沖田の声色は硬かった。
相手が好戦的でないと分かったからといって、その態度を一切軟化させることはなかった。依然としてその佇まいは鋭い刃そのものだ。
否――寧ろ硬質化しているようにさえ聞こえた。
恐らくそれは彼女の出自が関連しているのだろう。幕末の京都において、それこそ正義など硬貨の裏表のようなものだったことは想像に難くない。
相手が好戦的でないと分かったからといって、その態度を一切軟化させることはなかった。依然としてその佇まいは鋭い刃そのものだ。
否――寧ろ硬質化しているようにさえ聞こえた。
恐らくそれは彼女の出自が関連しているのだろう。幕末の京都において、それこそ正義など硬貨の裏表のようなものだったことは想像に難くない。
「はい、私たちは正義のために戦っています。
たとえ時代が違うとしても、無辜の人々を傷つける悪がそこにいるのであれば――私は街を、そして人を守ります。
貴方も英雄であれば、その心は変わらない筈でしょう?」
「では聞きますが――何故私たちを?」
「それは……他の陣営とは、交渉できるようには思えなかったからなんです。
バーサーカーやアサシンは論外。ライダーも腹の底が読めませんでした。吸血鬼に至っては理解不能です。
キャスターはもしかすると協力してくれたかもしれませんが……彼らの場合はそもそもどこにいるのかが分かりません。
少なくとも私たちが知り得ている中では――」
「――最も組し易い。そう見られた訳ですね」
たとえ時代が違うとしても、無辜の人々を傷つける悪がそこにいるのであれば――私は街を、そして人を守ります。
貴方も英雄であれば、その心は変わらない筈でしょう?」
「では聞きますが――何故私たちを?」
「それは……他の陣営とは、交渉できるようには思えなかったからなんです。
バーサーカーやアサシンは論外。ライダーも腹の底が読めませんでした。吸血鬼に至っては理解不能です。
キャスターはもしかすると協力してくれたかもしれませんが……彼らの場合はそもそもどこにいるのかが分かりません。
少なくとも私たちが知り得ている中では――」
「――最も組し易い。そう見られた訳ですね」
沖田はそう短く切り捨てた。
同時に「マスター」と呼びかける。
口上はどうでもいいので茜の判断を仰ぐ――そんな心積もりなのだろう。
同時に「マスター」と呼びかける。
口上はどうでもいいので茜の判断を仰ぐ――そんな心積もりなのだろう。
「私たちは同盟に特に条件など設けません。
ただ聖杯を破壊する――という一点に同意していただければ、私のマスターも姿を見せます。
ただ――バーサーカーの相手は私がするつもりです」
ただ聖杯を破壊する――という一点に同意していただければ、私のマスターも姿を見せます。
ただ――バーサーカーの相手は私がするつもりです」
最後の一言のみ、声のトーンが僅かに変わっていることに茜は気づいた。
どうやらこのセイバーはあの鬼面のバーサーカーと深い因縁があるようだ。
正直そこは――どうでもいい。
茜たちもあのバーサーカーとは初日より何度か戦っているが、敵に興味など端からない。
どうやらこのセイバーはあの鬼面のバーサーカーと深い因縁があるようだ。
正直そこは――どうでもいい。
茜たちもあのバーサーカーとは初日より何度か戦っているが、敵に興味など端からない。
短期視野に立って考えるのならば、この同盟は悪い話ではない。
そのことは考えるもまでもない。魔術について何も知らぬ自分が、どうも情報に通じているらしい陣営と接触できることは、それだけで価値があることだ。
とはいえ――そこも本質的にはどうでもいいことだ。
そのことは考えるもまでもない。魔術について何も知らぬ自分が、どうも情報に通じているらしい陣営と接触できることは、それだけで価値があることだ。
とはいえ――そこも本質的にはどうでもいいことだ。
ここで悩むべきは――彼女が口にした正義のことだ。
あるいはそう――個と言い換えてもいい。
主張するべき自己、擁立すべき秩序――ともすればバラバラになりそうになる想いを彼女は正義という一言でまとめている。
それが彼女の個であり、律である。個と社会を正義という言葉で結びつけ、それが人格を形成している。
あるいはそう――個と言い換えてもいい。
主張するべき自己、擁立すべき秩序――ともすればバラバラになりそうになる想いを彼女は正義という一言でまとめている。
それが彼女の個であり、律である。個と社会を正義という言葉で結びつけ、それが人格を形成している。
茜が悩むべきことは――その強さだ。
あまりにも強い個の隣で――茜は果たして如何な個を保てばいいのか。
実際、茜は聖杯などどうでもいいと思っている。あの黒衣の男との対峙を経た今となっては願いなどありはしない。
しかしだからといって壊そうなどとも思いはしない。茜にしてみれば、それもまた十分な個――願いであり、欲求だからだ。
あまりにも強い個の隣で――茜は果たして如何な個を保てばいいのか。
実際、茜は聖杯などどうでもいいと思っている。あの黒衣の男との対峙を経た今となっては願いなどありはしない。
しかしだからといって壊そうなどとも思いはしない。茜にしてみれば、それもまた十分な個――願いであり、欲求だからだ。
――いや、それ以上の願いとさえ言えるだろう。
聖杯戦争、というシステムが既に構築されており、それに反する動きを取るのだ。
そうした側面を見れば、ルールに沿って願いを叶えようとするのは、あくまでシステムの渦中にいる者の考えに過ぎない。
既に敷かれたシステムへの破壊などというのは相応の個の強さがなくてはできない――茜の、死んだ妹のように。
そうした側面を見れば、ルールに沿って願いを叶えようとするのは、あくまでシステムの渦中にいる者の考えに過ぎない。
既に敷かれたシステムへの破壊などというのは相応の個の強さがなくてはできない――茜の、死んだ妹のように。
「一つ、試したいことができました」
そこで茜の煩悶に気づいたのだろう、代わりと言うべきか、沖田が口を開いていた。
そして彼女は――静かに刀を抜いていた。
瞬間、もう一人のセイバーの顔色が変わった。
そして彼女は――静かに刀を抜いていた。
瞬間、もう一人のセイバーの顔色が変わった。
「私、貴方たちの力量が知りたくなってきました。
確かに貴方のマスターはそれなりに力量のある魔術師なのでしょう。
私たちを遠くから観察したり、どんな手段かは知りませんが人払いの魔術を使っていたり、本当便利ですよねぇ」
確かに貴方のマスターはそれなりに力量のある魔術師なのでしょう。
私たちを遠くから観察したり、どんな手段かは知りませんが人払いの魔術を使っていたり、本当便利ですよねぇ」
そこまで言われて――茜は気づいた。
辺りには人影が見えなくなっていることを。
さきほどまではいた筈の観光客や子どもの姿が見えなくなっている。
あるのは勢いよく流れる鴨川と、延々と桜が降り注ぐ道だけだ……
辺りには人影が見えなくなっていることを。
さきほどまではいた筈の観光客や子どもの姿が見えなくなっている。
あるのは勢いよく流れる鴨川と、延々と桜が降り注ぐ道だけだ……
「しかし――だからといって貴方たちが強いってことにはなりませんからね」
他に誰もいない桜の道で、沖田はそんなことを言った。
「正義結構。聖杯破壊結構。しかし戦場に事の善悪なし――私が同盟相手として気にするのはその力量です。
少なくとも、かつてこの京の都で信じられたのはそれだけでしたから。
だから同盟を求める以上、力を見せて欲しいと思います。こう言い換えてもいいでしょう――」
少なくとも、かつてこの京の都で信じられたのはそれだけでしたから。
だから同盟を求める以上、力を見せて欲しいと思います。こう言い換えてもいいでしょう――」
――その刀の斬れ味はどの程度のものですか?
と。
沖田はどこか挑戦的な口調で問いかけた。
それに対し、もう一人のセイバーは抜刀の音で答えた。
沖田はどこか挑戦的な口調で問いかけた。
それに対し、もう一人のセイバーは抜刀の音で答えた。
「なるほど、見たところ貴方も一人の剣客。そう思うのも無理はありませんね」
「そういう貴方は――ただの人斬りではないようですね。正義の人斬りなんていたら笑っちゃいますけど」
「そういう貴方は――ただの人斬りではないようですね。正義の人斬りなんていたら笑っちゃいますけど」
そうして相対した二人の少女の間を、風が吹き抜ける。
途端、頭上より一斉に桜の花びらが舞っていく。その勢いたるや灰色のアスファルトを埋め尽くすほどであった。
その桜吹雪に合わせるかのようにして少女たちの和装もはためく。
はらり、はらりと――
途端、頭上より一斉に桜の花びらが舞っていく。その勢いたるや灰色のアスファルトを埋め尽くすほどであった。
その桜吹雪に合わせるかのようにして少女たちの和装もはためく。
はらり、はらりと――
「――行きます」
重なる声と共に、二人の少女は地を蹴り――そして交錯した。
これより二人は敵と味方になる。少なくとも数分間は――
これより二人は敵と味方になる。少なくとも数分間は――
◇
――行きます。
その言葉はどちらのものだったか。
あるいは本当に声に出して発せられたものであったのか。ただ意識が勝手に掛け声のようなものを捏造しただけなのかもしれない。
何にせよ――
あるいは本当に声に出して発せられたものであったのか。ただ意識が勝手に掛け声のようなものを捏造しただけなのかもしれない。
何にせよ――
――斬るのみ。
力試し、という名目であるが、沖田総司に寸止めや峰打ちなどという力の抜き方はできない。
生かすか殺すか、その二択しかない。そしてサーヴァントとして真剣を振るう以上、できる手加減は殺しの質――殺意の純度を下げることくらいだ。
故に彼女は――間違いなく殺すつもりで駆け出していた。
生かすか殺すか、その二択しかない。そしてサーヴァントとして真剣を振るう以上、できる手加減は殺しの質――殺意の純度を下げることくらいだ。
故に彼女は――間違いなく殺すつもりで駆け出していた。
風のように速い、という表現がある。
武田信玄の“風林火山”やその基である孫子の“故其疾如風”などを引用するまでもなく、風、というものは古来より速きもの、軽やかなものとして人に認識されてきた。
瞬く間にやってきて、すぐさまどこかへと消え去ってしまう。来るときも去るときも一瞬。それが風と言うものである。
しかし沖田総司の剣の表現として、その表現は正しくないだろう。
武田信玄の“風林火山”やその基である孫子の“故其疾如風”などを引用するまでもなく、風、というものは古来より速きもの、軽やかなものとして人に認識されてきた。
瞬く間にやってきて、すぐさまどこかへと消え去ってしまう。来るときも去るときも一瞬。それが風と言うものである。
しかし沖田総司の剣の表現として、その表現は正しくないだろう。
何故ならば――
「――はっ」
――沖田総司が駆け抜けるのに、一瞬は少々長過ぎる。
「――――」
敵、もう一人のセイバーには、地を蹴る音と同時に沖田の剣が放たれた――と見えたに違いない。
当初、二人のセイバーの間は十五尺は空いていた。
この距離の取り方は話し合いのためだろう。向こうはこちらを無暗に刺激したくなかったことが窺える。
そして二人の背丈が共に五尺一寸、二寸程度であることを考えれば、当然共にまだ“届かぬ”間合いだった。
この距離の取り方は話し合いのためだろう。向こうはこちらを無暗に刺激したくなかったことが窺える。
そして二人の背丈が共に五尺一寸、二寸程度であることを考えれば、当然共にまだ“届かぬ”間合いだった。
しかし――沖田にしてみれば、それは“制空権”なのである。
縮地。沖田が身に着けているそのスキルはランク如何によっては次元すら越えるという。
彼女の剣を風で表現するのならばこうするべきだろう。
――沖田総司は風よりも速い。
と。
縮地。沖田が身に着けているそのスキルはランク如何によっては次元すら越えるという。
彼女の剣を風で表現するのならばこうするべきだろう。
――沖田総司は風よりも速い。
と。
もう一人のセイバーが目を見開いた――だがそれでもなお反応していた。
金属音。
刃と刃が交錯する音が響き、そして――再び沖田は最初の位置――茜の前へと舞い戻っていた。
金属音。
刃と刃が交錯する音が響き、そして――再び沖田は最初の位置――茜の前へと舞い戻っていた。
「……速い」
敵は端的にそう述べつつも、沖田の圧倒的な速さに気おくれした様子はなかった。そして事実、彼女は沖田の初撃を受けて見せたのだ。
ただ毅然と沖田と相対しつつ、彼女は上段に刀を構える。
ただ毅然と沖田と相対しつつ、彼女は上段に刀を構える。
「北辰一刀流ですか」
その構えを見た沖田がぽつりと漏らした。
――北辰一刀流。
更に原型たる一刀流は現代より遡ること五百年、戦国期に現れた伊藤一刀斎景久が租であった。
彼の門弟であった御子神典膳が徳川家に召し抱えられたことで、将軍家の流儀として天下にその名を轟かせることになった。
一刀流はその後、様々な流派に派生していく訳であるが、その過程で千葉周作が浅利又七郎から一刀流を学ぶ。
彼の門弟であった御子神典膳が徳川家に召し抱えられたことで、将軍家の流儀として天下にその名を轟かせることになった。
一刀流はその後、様々な流派に派生していく訳であるが、その過程で千葉周作が浅利又七郎から一刀流を学ぶ。
そしてこの千葉周作こそ――北辰一刀流を確立させた剣術家である。
一刀流を学んだ周作は、その流派を祖父が収めていた北辰夢想流と折衷することを思いついた。
他の派生流派と一線を画す特徴として、北辰一刀流は“実戦派”であったといえるだろう。
開祖たる伊藤一刀斎景久の時代から二百年が経っていた当時、天下泰平の江戸時代ということもあり、机上の空論染みた技などが跋扈していた。
他の派生流派と一線を画す特徴として、北辰一刀流は“実戦派”であったといえるだろう。
開祖たる伊藤一刀斎景久の時代から二百年が経っていた当時、天下泰平の江戸時代ということもあり、机上の空論染みた技などが跋扈していた。
それを周作は実戦的な“体系(システム)”に落とし込み、流派そのものの徹底的な簡略化と合理化を行ったのだ。
これが如何に有効であったかは言うまでもない。
最も稽古に竹刀を導入したことで、稽古と実戦の間にロジックの乖離が起こってしまう事態も発生したが――幕末期にも数多くの猛者が排出された。
これが如何に有効であったかは言うまでもない。
最も稽古に竹刀を導入したことで、稽古と実戦の間にロジックの乖離が起こってしまう事態も発生したが――幕末期にも数多くの猛者が排出された。
「――また因果な流派が出てきたものです」
相対するセイバーの構えに対し、そこで沖田はそう漏らした。
北辰一刀流と新撰組、そして引いては沖田との因縁は案外深い。
北辰一刀流と新撰組、そして引いては沖田との因縁は案外深い。
新撰組内にも多くの出身者がいた。そもそも初代局長たる芹沢鴨からして北辰一刀流だった。
そして古株であり副長であった山南敬介も、その同門で組内で発言力のあった伊東甲子太郎も北辰一刀流であった。
みな新撰組に深く関わっていた人物だ。
そして古株であり副長であった山南敬介も、その同門で組内で発言力のあった伊東甲子太郎も北辰一刀流であった。
みな新撰組に深く関わっていた人物だ。
――全員、斬り殺したんですけどね。
彼らはみな、他でもない新撰組の手で斬られている。
沖田はそのことに対して、別段深い感慨はない。
自分は人斬りに過ぎず、善しであるか悪しであるかを考える役目にはない。
土方や近藤がそう判断したのであれば、それに従うだけだ。
最も――山南をこの手で斬った時だけは、少々別の感情が芽生えたものだが。
沖田はそのことに対して、別段深い感慨はない。
自分は人斬りに過ぎず、善しであるか悪しであるかを考える役目にはない。
土方や近藤がそう判断したのであれば、それに従うだけだ。
最も――山南をこの手で斬った時だけは、少々別の感情が芽生えたものだが。
それに北辰一刀流が必ず敵だったという訳でもない。
藤堂平助や吉村貫一郎もまた北辰一刀流だった筈だ。
そして何より――天才剣士たる彼女自身もまた、北辰一刀流の免許皆伝を受けている。
藤堂平助や吉村貫一郎もまた北辰一刀流だった筈だ。
そして何より――天才剣士たる彼女自身もまた、北辰一刀流の免許皆伝を受けている。
――ああそういえば、坂本さんもでしたっけ。
沖田は生前出会った一人の男のことを想い返しつつ、二撃目の態勢へと移る。
構えは上段。向こうと同じく攻撃的な構えだ。
ふっ、と息を吸い――そして再び彼女は駆け抜けた。
それをもう一人のセイバーは果敢にも正面から受けんとする。
構えは上段。向こうと同じく攻撃的な構えだ。
ふっ、と息を吸い――そして再び彼女は駆け抜けた。
それをもう一人のセイバーは果敢にも正面から受けんとする。
――速く
縮地。
桜舞う世界を滑るようにして沖田は剣を振るう。
その件の流派は――天然理心流だった。
それは“天に象り、地に法り、以て剣理を究める”の文言が象徴するように、自然の法則に逆らわず極意に達するという流派である。
農民剣法、などと時には揶揄されることもあるが、幕臣にも数多くの門人がおり、農民だけが収める流派では決してなかった。
桜舞う世界を滑るようにして沖田は剣を振るう。
その件の流派は――天然理心流だった。
それは“天に象り、地に法り、以て剣理を究める”の文言が象徴するように、自然の法則に逆らわず極意に達するという流派である。
農民剣法、などと時には揶揄されることもあるが、幕臣にも数多くの門人がおり、農民だけが収める流派では決してなかった。
――鋭く
とはいえ――新撰組の、特に近藤や土方らが収めていた剣は間違いなく泥に塗れていた。
剣を磨くのは、ひとえに敵を殺すため。
また彼らにとって剣は人を殺すための一つの手段に過ぎない。それで敵を殺せるのなら何を使ってもいいのだ。
剣を磨くのは、ひとえに敵を殺すため。
また彼らにとって剣は人を殺すための一つの手段に過ぎない。それで敵を殺せるのなら何を使ってもいいのだ。
そんな沖田が敢えて正面から剣を向けているのは確信しているからだった。
先の一合の斬り合いだけで沖田は敵の力量を見抜いていた。
このセイバーは――速さ、即ち剣の腕に関しては自分よりも下だと。
決して技量が低い訳ではない。その修練度は幕末期に活躍していた浪士たちと比しても見劣りしないものだ。
先の一合の斬り合いだけで沖田は敵の力量を見抜いていた。
このセイバーは――速さ、即ち剣の腕に関しては自分よりも下だと。
決して技量が低い訳ではない。その修練度は幕末期に活躍していた浪士たちと比しても見劣りしないものだ。
けれど――届かない。
この京都に名を轟かせた壬生浪士。
その中で最強と評された剣士の域には――とてもではないが到達できてはいない。
その中で最強と評された剣士の域には――とてもではないが到達できてはいない。
故に折られる筈だった。
咲き乱れる桜も何時かは墜ちて泥に塗れるように、当然の帰結としてもう一人のセイバーは敗れる筈だった。
咲き乱れる桜も何時かは墜ちて泥に塗れるように、当然の帰結としてもう一人のセイバーは敗れる筈だった。
けれど――
「破邪剣征――」
――沖田の知る北辰一刀流は、あくまで“表”のものだけだった。
このセイバーは、もちろん“表”の北辰一刀流も収めていたが、しかし――彼女が英霊として昇華されたのは一重に“裏”があったからである。
表層化しなかった“裏”の北辰一刀流こそ、彼女が英霊となる運命を決定づけたものだった。
表層化しなかった“裏”の北辰一刀流こそ、彼女が英霊となる運命を決定づけたものだった。
「――桜花放神」
その自体は、抜刀術であるに沖田には見えた。
刀を鞘に納め、力を溜めるようにして沖田を待っている。
それ自体は何らおかしなことではない。とかく速過ぎる沖田に対し、抜刀術で迎撃で対抗と言うのは事実有効ではある。
刀を鞘に納め、力を溜めるようにして沖田を待っている。
それ自体は何らおかしなことではない。とかく速過ぎる沖田に対し、抜刀術で迎撃で対抗と言うのは事実有効ではある。
しかし――その構えはただの剣ではなかった。
構える彼女の周りに、ぼう、と神秘的な光が灯っている。
それは刹那のやり取りが見せる錯覚などではない。確かに存在する神秘として、その光は辺りを照らしているのだ。
その証拠に――桜の花びらの一つ一つにまで光は伝播し、その色彩を変えてしまっている。
淡紅色の儚い色彩から、陽の光にも似た橙色へと――
構える彼女の周りに、ぼう、と神秘的な光が灯っている。
それは刹那のやり取りが見せる錯覚などではない。確かに存在する神秘として、その光は辺りを照らしているのだ。
その証拠に――桜の花びらの一つ一つにまで光は伝播し、その色彩を変えてしまっている。
淡紅色の儚い色彩から、陽の光にも似た橙色へと――
「はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
――その声と共に、辺りに舞った神秘の光は収束し、光の刃となった。
沖田は、はっ、としてその身を転進させた。
ぶうん、と音が勢いよく鳴り響く。刃が抉りとったアスファルトの破片がぱらぱらと舞った。
ぶうん、と音が勢いよく鳴り響く。刃が抉りとったアスファルトの破片がぱらぱらと舞った。
「……魔術の類を使うとは思いませんでした」
マスターたる茜を片手で抱えながら、今しがた放たれた技に対し沖田がそう評した。
技が発動しようとするまでの僅かな隙間に後退し、マスターの安全を確保していたのである。
最も、その剣の射線(というべきだろう)は、茜からはずれており、その心配は杞憂だったのだが。
偶然ではなく故意に外したのだろうと沖田は、相対する少女の眼差しを見て確信する。
技が発動しようとするまでの僅かな隙間に後退し、マスターの安全を確保していたのである。
最も、その剣の射線(というべきだろう)は、茜からはずれており、その心配は杞憂だったのだが。
偶然ではなく故意に外したのだろうと沖田は、相対する少女の眼差しを見て確信する。
「なるほどそれが――貴方をただの人斬りでなく、正義の味方足らせているのですね」
「この力が――私の運命でした。この力があったからこそ、私は運命に向き合い、そしてあの時――」
「この力が――私の運命でした。この力があったからこそ、私は運命に向き合い、そしてあの時――」
そこでもう一人のセイバーは言葉を切った。ここで語るべきことではないと悟ったのだろう。
代わりに、彼女は沖田から視線を外し、
代わりに、彼女は沖田から視線を外し、
「――さて、これでどうです? そちらのマスターさん。
私の力量には満足できましたか?」
私の力量には満足できましたか?」
◇
桜が舞っていた。
今しがた桜がふり注ぐ中で行われた、少女剣士たちの攻防。
その凄烈なやり取りは、とてもではないが全て知覚できなかった。
その凄烈なやり取りは、とてもではないが全て知覚できなかった。
だから――桜が舞っていたのだ。
そう表現するにふさわしい、と茜は思う。
新世紀の風が吹くこの古都で、かつてこの国に咲いていたであろう桜たちが交錯する。
その美しさは、それ以上の言葉で糊塗するのは無粋であろう。
新世紀の風が吹くこの古都で、かつてこの国に咲いていたであろう桜たちが交錯する。
その美しさは、それ以上の言葉で糊塗するのは無粋であろう。
とはいえ――茜が気にかかっていたのは別のことであった。
「――さて、これでどうです? そちらのマスターさん。
私の力には満足頂けましたか?」
私の力には満足頂けましたか?」
そう問いかけてくるセイバーの表情は、剣の色など見えない可憐な少女そのものだ。
そして――茜には分かってしまう。正義を信じるこの少女を、どうすれば自分の都合の良い方向へと導くことができるかを。
そして――茜には分かってしまう。正義を信じるこの少女を、どうすれば自分の都合の良い方向へと導くことができるかを。
――破邪剣征・桜花放神
先ほどこのセイバーが口にした技。
茜は特段剣術などに興味はない。かような技を知る由もない。
しかしそんな彼女であっても、その言葉をしっかりと聞き取り、反芻することができた。
茜は特段剣術などに興味はない。かような技を知る由もない。
しかしそんな彼女であっても、その言葉をしっかりと聞き取り、反芻することができた。
何故ならば――既に見ているからだ。
この一週間で、同じ技を使う者に幾度か茜はその身を狙われている。
あの鬼面のバーサーカーが――それだ。
加えて、先ほどこのセイバーに見せたバーサーカーへの執着を想うと――
この一週間で、同じ技を使う者に幾度か茜はその身を狙われている。
あの鬼面のバーサーカーが――それだ。
加えて、先ほどこのセイバーに見せたバーサーカーへの執着を想うと――
「――私は、マスターの移行に従いますよ。
聖杯を獲るにせよ、壊すにせよ、どちらも私にとっては戦いですから」
聖杯を獲るにせよ、壊すにせよ、どちらも私にとっては戦いですから」
沖田、茜のセイバーもまたそう言ってくれる。
先の人斬りの顔とは打って変わって無垢な微笑みを浮かべながら。
しかし、それもまた茜には分かってしまうのだ。
先の人斬りの顔とは打って変わって無垢な微笑みを浮かべながら。
しかし、それもまた茜には分かってしまうのだ。
彼女らの――理(ことわり)というものが。
そしてこの聖杯戦争という盤面も全貌も見えてきた。
今までの五里霧中の状態から、視界が徐々に晴れてきたことを彼女は感じていた。
そしてこの聖杯戦争という盤面も全貌も見えてきた。
今までの五里霧中の状態から、視界が徐々に晴れてきたことを彼女は感じていた。
聖杯戦争と言う盤面は分かった。そのルールも掴めてきた。
そこに生きる者たちの顔も見えてきた。システムの中にいる因子(ファクター)たちの理もまた、把握しつつある。
全容を把握する必要などない。ただ無秩序に動く因子たちが、因子を再排出するような、そんなシステムを構築してやればいい。
そこに生きる者たちの顔も見えてきた。システムの中にいる因子(ファクター)たちの理もまた、把握しつつある。
全容を把握する必要などない。ただ無秩序に動く因子たちが、因子を再排出するような、そんなシステムを構築してやればいい。
――ああ、これは。
■■の理だと、茜は自覚する。
これは――無意味な理だ。手段だけが思いつくのに、その先にあるべき願いが、個がないのでは――
これは――無意味な理だ。手段だけが思いつくのに、その先にあるべき願いが、個がないのでは――
――個など、そもそも存在しないのではないか。
絶対的な個などそもそもありはしないだろう。
どうやっても対外的な想念が個には発生する。システムに対してどう動くか、その要素抜きで人の個は語れない。
ならば――■■でしかない者は。
どうやっても対外的な想念が個には発生する。システムに対してどう動くか、その要素抜きで人の個は語れない。
ならば――■■でしかない者は。
「……マスター?」
その時、沖田が訝しげに尋ねてきた。
狂ったように降りしきる桜の中、立ち尽くす茜に対し彼女は、
狂ったように降りしきる桜の中、立ち尽くす茜に対し彼女は、
「何で泣いてるんですか?」
その時になって、茜は初めて自分が泣いていることに気づいた。
[2004年/8日目/午前/京都左京区下鴨半木町・半木の道]
【織作茜@塗仏の宴】
[状態]健康・魔力消耗(大)
[装備]なし
[道具] なし
[所持金] 不明
[思考・状況]
基本行動方針:???
1:私は――
[備考]
※時期は【塗仏の宴 宴の始末】開始前です。
[状態]健康・魔力消耗(大)
[装備]なし
[道具] なし
[所持金] 不明
[思考・状況]
基本行動方針:???
1:私は――
[備考]
※時期は【塗仏の宴 宴の始末】開始前です。
【セイバー(沖田総司)@Fate/Grand Order】
[状態] 健康
[装備] 乞食清光
[道具] なし
[思考・状況]
基本行動方針: 最後まで戦い抜く
1. マスターに従いますが?
[備考]
※遂にコハエース出典じゃなくなりました。やったー
※ぶっちゃけバーサーカーはどうでもいい
[状態] 健康
[装備] 乞食清光
[道具] なし
[思考・状況]
基本行動方針: 最後まで戦い抜く
1. マスターに従いますが?
[備考]
※遂にコハエース出典じゃなくなりました。やったー
※ぶっちゃけバーサーカーはどうでもいい
【セイバー(???)@???】
[状態] 健康
[装備] ???
[道具] なし
[思考・状況]
基本行動方針:正義のために、戦います。
1. あのバーサーカーは――
[備考]
※全体的に沖田に似ていますが、黒髪です。
※ステータスは敏捷は沖田に劣りますが、耐久・魔力では圧倒しています。
[状態] 健康
[装備] ???
[道具] なし
[思考・状況]
基本行動方針:正義のために、戦います。
1. あのバーサーカーは――
[備考]
※全体的に沖田に似ていますが、黒髪です。
※ステータスは敏捷は沖田に劣りますが、耐久・魔力では圧倒しています。