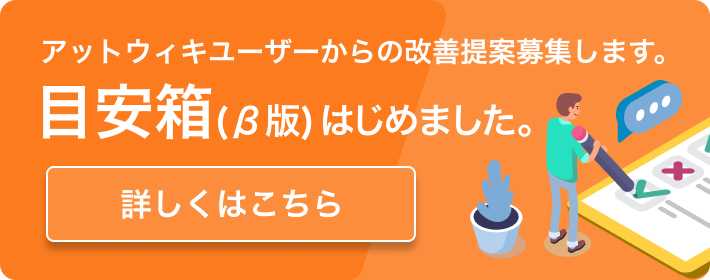【空白のなかの聖杯戦争】
『蝉時雨/あなただけ、Dreaming』
首都――東京。
真夏の日差しが、この街を見下ろしていた。
この夏、何度目かの最高気温は、人々の目の中で蜃気楼を生み出し、街並を包み込んで蕩けさせていく。
ビルが歪んだ。風がなかった。汗が滲んだ。セミが喚いた。
歩く足が重かったが、雑踏は誰かが立ち止まる事を許さなかった。
その雑踏の中にいる誰もがきっと、立ち止まりたいと思っていた筈だが、同時に急いで目的地にたどり着きたいとも思っていた。
だから、やはり自分以外の誰かが立ち止まるのを快く思ってはくれなそうだった。
この夏、何度目かの最高気温は、人々の目の中で蜃気楼を生み出し、街並を包み込んで蕩けさせていく。
ビルが歪んだ。風がなかった。汗が滲んだ。セミが喚いた。
歩く足が重かったが、雑踏は誰かが立ち止まる事を許さなかった。
その雑踏の中にいる誰もがきっと、立ち止まりたいと思っていた筈だが、同時に急いで目的地にたどり着きたいとも思っていた。
だから、やはり自分以外の誰かが立ち止まるのを快く思ってはくれなそうだった。
わたしもまた、その中で立ち止まった。振り返る事も許されなかった。
そう、今日とまったく同じ天気だった、あの夏の事……。
聖杯戦争、と呼ばれたあの不思議な日々の事を……。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
小学六年生の頃のわたし――『香月舞』は、どういうわけか知らないが、聖杯戦争という奇妙な儀式に参加させられていた。
聖杯戦争について簡単に説明すると、それは願いを叶える為の願望器『聖杯』を得る為に、魔術師たちが英霊を呼び出して戦い合い最後の一人を決めるという『戦争』だ。――本来なら「願い」がある人間に差し出されるような儀式のはずだが、わたしにはそんな願いはなかったので、その時にはひどく場違いな気持ちになった。
こう断言してしまうと語弊があるので一応言っておくと、わたしにも当時から抱いていた夢自体はあった。つまり、将来の夢がない子供ではなかったし、その夢に対して中途半端な志しか持たないわけでもなかったのだ。
しかし、その夢を叶える手段として、聖杯を使う事を望んでいなかった。それに、現実にその夢を叶える手法は人の命を対価にするほど大袈裟な事でなかった。
事実、参加者たちの中にも聖杯を得る理由はさまざまあったが、わたしが見てきた数名の『敵』の中には、亡き恋人に捧げようとした人や、平和を築く為に使おうとした人がいた。――やはり、ほとんどは、一個人の努力では叶わない『悲願』を託す人たちであり、その人たちの最後のよりどころが聖杯なのだろうと思う。
聖杯戦争について簡単に説明すると、それは願いを叶える為の願望器『聖杯』を得る為に、魔術師たちが英霊を呼び出して戦い合い最後の一人を決めるという『戦争』だ。――本来なら「願い」がある人間に差し出されるような儀式のはずだが、わたしにはそんな願いはなかったので、その時にはひどく場違いな気持ちになった。
こう断言してしまうと語弊があるので一応言っておくと、わたしにも当時から抱いていた夢自体はあった。つまり、将来の夢がない子供ではなかったし、その夢に対して中途半端な志しか持たないわけでもなかったのだ。
しかし、その夢を叶える手段として、聖杯を使う事を望んでいなかった。それに、現実にその夢を叶える手法は人の命を対価にするほど大袈裟な事でなかった。
事実、参加者たちの中にも聖杯を得る理由はさまざまあったが、わたしが見てきた数名の『敵』の中には、亡き恋人に捧げようとした人や、平和を築く為に使おうとした人がいた。――やはり、ほとんどは、一個人の努力では叶わない『悲願』を託す人たちであり、その人たちの最後のよりどころが聖杯なのだろうと思う。
結局、あれからどれだけ歳月を重ねても、当時ただの子供だったわたしがあの儀式に参加させられた理由はわからないままだ。しかし、「理由」を追い求めるにも、既に時間は経ち過ぎているので、わたしはとっくに真相を知るのを諦めて、あれが『卒業の儀礼』だったと思い込む事にしていた。
ふつう、小学生の子供たちが卒業記念にそんな儀礼を行う事などない筈だし、実際にそうなったのはわたしだけなのだろうけど、それでもそういう風に思い込む事で強引に答えを作り出したのだ。
あれは、わたしにとっての一つのきっかけなのだと――今のわたしはそう思う事にしている。
ふつう、小学生の子供たちが卒業記念にそんな儀礼を行う事などない筈だし、実際にそうなったのはわたしだけなのだろうけど、それでもそういう風に思い込む事で強引に答えを作り出したのだ。
あれは、わたしにとっての一つのきっかけなのだと――今のわたしはそう思う事にしている。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
【1986/08/31】
聖杯戦争の開始から一ヶ月が過ぎ去り、そして遂に終わりの日を迎えた時――あの最後の日の事だけを、わたしは思い返す事ができる。
三十一日もの長い聖杯戦争のなかで、いくつもの懐かくも悲しいエピソードがあるのだが、今のわたしにはそれを頭の中で時系列順に並べ替える事はできないし、わたしの記憶はきっと時間によって多くを書き換えられてしまっているのだ。だから、わたしにとって聖杯戦争として正確といえる思い出は、「最初の日」――八月一日と「最後の日」――八月三十一日、その二日間だけなのである。
三十一日もの長い聖杯戦争のなかで、いくつもの懐かくも悲しいエピソードがあるのだが、今のわたしにはそれを頭の中で時系列順に並べ替える事はできないし、わたしの記憶はきっと時間によって多くを書き換えられてしまっているのだ。だから、わたしにとって聖杯戦争として正確といえる思い出は、「最初の日」――八月一日と「最後の日」――八月三十一日、その二日間だけなのである。
始めは、理不尽な強制参加と言って然るべき物であったが、なぜか自然とわたしは生き延びていて、聖杯戦争の最後の朝日を拝む事になった。
それまでの一ヶ月、マスターとして結構な苦労をしてきたつもりだが、他の何十人もの参加者もその点では同じだったので、やはりわたしが生き延びる事が出来たのは奇跡的な事だっただろう(まして、わたしのサーヴァントは、これといって逸話のないほとんど無名の青年なのだから、余計に奇跡的である)。
もう一人生き残っているマスターのジョン・マクレーンというアメリカの刑事の方は、もともと多くの事件に巻き込まれながら生き残り続けた特殊な運勢の持ち主だった事もあり、余計にわたしだけがラッキーを背負えているのは奇妙に見えた。
わたしたちの直面した脅威の中には、別の誰かの犠牲によって逃れる事ができた物もあったので、本当はただのラッキーで済ませてしまうのは自分の中でもかなり複雑なのだけど、あれから時間が経つとやはりその言葉で片づけるしか仕様がなくなってしまう。
それまでの一ヶ月、マスターとして結構な苦労をしてきたつもりだが、他の何十人もの参加者もその点では同じだったので、やはりわたしが生き延びる事が出来たのは奇跡的な事だっただろう(まして、わたしのサーヴァントは、これといって逸話のないほとんど無名の青年なのだから、余計に奇跡的である)。
もう一人生き残っているマスターのジョン・マクレーンというアメリカの刑事の方は、もともと多くの事件に巻き込まれながら生き残り続けた特殊な運勢の持ち主だった事もあり、余計にわたしだけがラッキーを背負えているのは奇妙に見えた。
わたしたちの直面した脅威の中には、別の誰かの犠牲によって逃れる事ができた物もあったので、本当はただのラッキーで済ませてしまうのは自分の中でもかなり複雑なのだけど、あれから時間が経つとやはりその言葉で片づけるしか仕様がなくなってしまう。
もしかすると、この聖杯戦争での生還は、不器用なわたしに神が授けてくれた――『もうひとつの魔法』のようなものかもしれない。
……あるいは、かつてわたしの前に現れた鏡の国の妖精が、この時もまた、どこかからわたしを見守っていてくれて、わたしの事を影ながら助けてくれていたのだろうか?
……あるいは、かつてわたしの前に現れた鏡の国の妖精が、この時もまた、どこかからわたしを見守っていてくれて、わたしの事を影ながら助けてくれていたのだろうか?
――とにかく、そんな加護を受けてか、最後の日の朝に目覚めた時も、わたしには自分が死ぬ予感など微塵もなかった。
ここまであらゆる脅威から逃げ切った安堵感と、自信とが強くなりつつあったのだ。唐突な死をすべて回避し、天寿を全うできる選ばれた人間であるような気さえしていた。
最初は死の恐怖に震えていた少女も、こうしていつの間にか死の予感を押し込めているのだから、まったく時の流れというのは不思議であっただろう。
ここまであらゆる脅威から逃げ切った安堵感と、自信とが強くなりつつあったのだ。唐突な死をすべて回避し、天寿を全うできる選ばれた人間であるような気さえしていた。
最初は死の恐怖に震えていた少女も、こうしていつの間にか死の予感を押し込めているのだから、まったく時の流れというのは不思議であっただろう。
それに、実際、最後の日というのは、いうなれば蛇足のような物でもあった。この前日までは、凶悪な敵と戦っていたが、その敵は倒され――最終日を目前にしながら消えてしまったので、わたしたちにとっての敵は、もう『聖杯戦争』という儀式そのものだけなのだ。
既に、サーヴァントとマスターはわたしたちを除いてもう一人ずつしか生き残っておらず、そちらのペアも聖杯の破壊を目的としていたのだから、わたしたちは協力関係を結び、実質的にもう殺し合いをリタイアしていたのである。
自分を狙うものがない以上、どこまでも安心した心持でいられるのは至極当然の事だった。
ただ、それでもどこか前夜はあまり眠れず過ごし、小学生時分のわたしには浅い微睡みのまま目を覚ました。
既に、サーヴァントとマスターはわたしたちを除いてもう一人ずつしか生き残っておらず、そちらのペアも聖杯の破壊を目的としていたのだから、わたしたちは協力関係を結び、実質的にもう殺し合いをリタイアしていたのである。
自分を狙うものがない以上、どこまでも安心した心持でいられるのは至極当然の事だった。
ただ、それでもどこか前夜はあまり眠れず過ごし、小学生時分のわたしには浅い微睡みのまま目を覚ました。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
……目覚めた時に窓の外で蝉がうるさく鳴いていたような覚えがあるが、それは果たして、記憶を都合よくノスタルジックに書き換えてしまった証なのか、わたしにはもうわからない。それでもこの時期は、まだ蝉たちは元気だったような気もする。
眠るわたしを見守っていたサーヴァント――いや、この呼び方は何だか他人行儀のような気がしてしまう、折角だから『東光太郎』さん……『光太郎さん』と呼ぼう――は、朝には既にどこかへいなくなっていた。
きっと、聖杯を解体する目的の為に聖杯のありかに行ったに違いなかった。
眠るわたしを見守っていたサーヴァント――いや、この呼び方は何だか他人行儀のような気がしてしまう、折角だから『東光太郎』さん……『光太郎さん』と呼ぼう――は、朝には既にどこかへいなくなっていた。
きっと、聖杯を解体する目的の為に聖杯のありかに行ったに違いなかった。
目覚めると、わたしの胸は、聖杯戦争を生き残った万能感とはまったく正反対の焦燥感も抱かれていた。
それは、聖杯戦争の終わりであると同時に、ちょうど、小学校最後の夏休みが、終わる――そんな想いが過る日でもあったからに違いない。つまりは、これまでの日常が確実に切り替わる起点に立った事を、その時、自覚したのだった。
結局は、中学に上がってからも、同じように長い夏休みを経験する筈だとわかっていたのに、何故かこの一日は朝から妙に貴重な気がして仕方がなかった。
幼心にも、小学校の夏休みと中学校の夏休みが決定的に違う物だと、どこかで予感できていたのかもしれない。
それは、聖杯戦争の終わりであると同時に、ちょうど、小学校最後の夏休みが、終わる――そんな想いが過る日でもあったからに違いない。つまりは、これまでの日常が確実に切り替わる起点に立った事を、その時、自覚したのだった。
結局は、中学に上がってからも、同じように長い夏休みを経験する筈だとわかっていたのに、何故かこの一日は朝から妙に貴重な気がして仕方がなかった。
幼心にも、小学校の夏休みと中学校の夏休みが決定的に違う物だと、どこかで予感できていたのかもしれない。
……おそらく、それは、この時流行っていた学園ドラマの中で描かれる「中学校像」と自分を見比べ、言い知れぬ危機感を覚えていたからだろうと思う。画面に映っている生徒たちは、真っ黒な制服を着ているだけで、「おにいさん」と「おねえさん」に見えていたし、体格が変わって化粧を施したお顔の「おねえさん」たちは、舞自身が自分の未来として見つめるにはあまりにも自分と違いすぎたのだ。
そして、そんな彼らは常に「ジュケン」や「ブカツ」との戦いをしていた。
これまで六年間で慣れてきた生活を全て手放して、行きつかなければならない未来にしては、どこか色調が暗く見えるのだった。
そして、そんな彼らは常に「ジュケン」や「ブカツ」との戦いをしていた。
これまで六年間で慣れてきた生活を全て手放して、行きつかなければならない未来にしては、どこか色調が暗く見えるのだった。
表向きは、「ああいう風になりたい」と――「早く大人になりたい」と思いながらも、その反面で「今」を手放したくない想いが、あの時のわたしの後ろ髪を引いていた。無限にあるように錯覚できる小学生の時間の中で、永久にその錯覚に陥り続けたかったのだ。
あるいは、その錯覚を捨て去る時期くらいは、自分の手で決めさせてほしいと思っていた――しかし、やはり最後の夏休みにも終わりが来てしまったのだ。
あるいは、その錯覚を捨て去る時期くらいは、自分の手で決めさせてほしいと思っていた――しかし、やはり最後の夏休みにも終わりが来てしまったのだ。
最後とはそういう意味だと、いくつかの出来事の中で知っていったが、やはり何度それに直面しても不安はぬぐわれる物ではなかった。
好きなテレビが終わる「最後」であったり、魔法を手放す決意を固めた「最後」であったり、祖父母の魔術団が解散する「最後」であったり……それを何度経験しても、そのたびに胸が苦しくなるのが小学生当時のわたしだった。
好きなテレビが終わる「最後」であったり、魔法を手放す決意を固めた「最後」であったり、祖父母の魔術団が解散する「最後」であったり……それを何度経験しても、そのたびに胸が苦しくなるのが小学生当時のわたしだった。
慣れ親しんだ環境を時の流れに任せて捨て去り、そして別の新しい自分に変わっていく事が怖くて仕方が無かった。
何より、「最後」という言葉の語感の中に、少しの「勿体無さ」を感じてしまうのである。
遠足の準備をする前に忘れ物がないか気になってしまうように、わたしは流れていく時の中でやり残した事がないか不安になっていた。聖杯戦争においても、小学生の夏休みにおいても、それは同じだった。
そんなわたしのもとに、二つの終わりがいっぺんに来たのだから、わたしは朝起きた時からそわそわして仕方が無かった。
何より、「最後」という言葉の語感の中に、少しの「勿体無さ」を感じてしまうのである。
遠足の準備をする前に忘れ物がないか気になってしまうように、わたしは流れていく時の中でやり残した事がないか不安になっていた。聖杯戦争においても、小学生の夏休みにおいても、それは同じだった。
そんなわたしのもとに、二つの終わりがいっぺんに来たのだから、わたしは朝起きた時からそわそわして仕方が無かった。
朝ごはんを食べる時、両親は、折角だから軽くどこかへ出かけようと言っていたが、わたしはそれを断った。弟の岬がつまらなそうに反論したのを、わたしはまだ覚えている。
友達の遊びの誘いの電話もあった気がするが、それもまた、わたしは断っていた。
友達の遊びの誘いの電話もあった気がするが、それもまた、わたしは断っていた。
この街で戦う彼らの――せめて、何も出来なくても近くにいようと思い、東京を離れなかったのである。
それが、その時わたしがやらなければならない、夏休みの最後の宿題だった。
それが、その時わたしがやらなければならない、夏休みの最後の宿題だった。
そう、彼らの帰りを待ち続ける事だけが……わたしの夏休みの宿題なのだ。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
今から思えば、自分に降りかかった状況に戸惑いだけを抱いていた少女は……もうこの時にはいなかったのだと思う。
聖杯戦争に順応しつつあり――、もしかすると大人よりもこなれていて――、時に戦いを忘れて笑えるような少女だけがいた。
聖杯戦争に順応しつつあり――、もしかすると大人よりもこなれていて――、時に戦いを忘れて笑えるような少女だけがいた。
……勿論、わたしも、聖杯戦争の過酷さをその日まで散々、目にしてきた。
親しくなった人の死も目の当たりにしたし、願いを抱えたまま叶わずに泣きながら死んでいく人の姿も見る事になった。祖父母の死だとか、飼っているペットの死だとか、そうした物も未経験に育ってきた未成熟児には、知っている命の最期は割り切れない唐突な悲しみでもあった。
親しくなった人の死も目の当たりにしたし、願いを抱えたまま叶わずに泣きながら死んでいく人の姿も見る事になった。祖父母の死だとか、飼っているペットの死だとか、そうした物も未経験に育ってきた未成熟児には、知っている命の最期は割り切れない唐突な悲しみでもあった。
しかし、この一ヶ月は、その連続でもあった。
心が痛んだが、壊れるほどではなかった。
親しい人の死は、いつか必ず目にする話で、それが来るのが早すぎただけだった。多くの人は、たとえ死に別れが早く来たとしても、その先の人生を生きている。
心が痛んだが、壊れるほどではなかった。
親しい人の死は、いつか必ず目にする話で、それが来るのが早すぎただけだった。多くの人は、たとえ死に別れが早く来たとしても、その先の人生を生きている。
それでも、人々が「過去」に惹かれ、時間に抵抗したくなる、最大の理由というのは、やはり「それ」なのだろう。
逃れられない死が近づいていく――そんな経過の中での気休めが、せめて意志だけでも時間に抵抗しようという想いなのだった。何かが壊れ、何かが終わるのを寂しく思うのは、きっと、それを通して死を見つめてしまうからだ。
しかし、どう抵抗しようとも本当にただの気休めで終わって、人間は決して時間には勝てない。
聖杯を獲ろうとした人たちの中にも、誰かの命を甦らせようと思った人がいた。――やはり、その人もまた、自分自身を取り巻く時間には勝てなかった。
逃れられない死が近づいていく――そんな経過の中での気休めが、せめて意志だけでも時間に抵抗しようという想いなのだった。何かが壊れ、何かが終わるのを寂しく思うのは、きっと、それを通して死を見つめてしまうからだ。
しかし、どう抵抗しようとも本当にただの気休めで終わって、人間は決して時間には勝てない。
聖杯を獲ろうとした人たちの中にも、誰かの命を甦らせようと思った人がいた。――やはり、その人もまた、自分自身を取り巻く時間には勝てなかった。
おそらく誰も、時間に勝つ事は出来ない。
せめて、そんな生命が時間に負けて、その後で行き着く先に、本当にまた別の世界――天国とかが広がっていればそれに越した事はないけど、それは今こうして生きているわたしには、全くわからない話なのだ。
だから、生まれて十何年か、あるいは、何十年か経つと、人は時間への恐怖に慣れ切ったように、いつか自分にも死が来る事を受け入れる。
せめて、そんな生命が時間に負けて、その後で行き着く先に、本当にまた別の世界――天国とかが広がっていればそれに越した事はないけど、それは今こうして生きているわたしには、全くわからない話なのだ。
だから、生まれて十何年か、あるいは、何十年か経つと、人は時間への恐怖に慣れ切ったように、いつか自分にも死が来る事を受け入れる。
そして――わたしのもとには、この時、少しだけ早く……ただしごく一時的に、その感覚が現れていたような気がした。
わたしは、ある意味で死に対して諦観していたのだ。何だか、いつしか終わっていく儚い運命も、素晴らしく美しい物のような気がしていた。
それは、狂気でも何でもなく普通の事だと思う。
だが、そんな考えは、聖杯戦争が終わってからまたしばらくすると消えていった。
今度はまたしばらく、普通の日常の中で、真夜中に襲い来る「死に対する唐突な恐怖」が現れるようになった。
しかし、また数年後には自然と真夜中にそんな嘆きを抱く事がなくなってしまった。今度は別に、一時的な物でもなくなっていた。
わたしは、ある意味で死に対して諦観していたのだ。何だか、いつしか終わっていく儚い運命も、素晴らしく美しい物のような気がしていた。
それは、狂気でも何でもなく普通の事だと思う。
だが、そんな考えは、聖杯戦争が終わってからまたしばらくすると消えていった。
今度はまたしばらく、普通の日常の中で、真夜中に襲い来る「死に対する唐突な恐怖」が現れるようになった。
しかし、また数年後には自然と真夜中にそんな嘆きを抱く事がなくなってしまった。今度は別に、一時的な物でもなくなっていた。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
わたしは、ほとんど習慣化していたマジックの練習すらも――その最終日に行う気が起きなかった。
一応やらなければならないと思って試してみたのに、指があまりにも震えて出来なかった。今の自分ならば動揺の中でも変わらず出来るほど指先に芸が刷り込まれているけれど、当時は今ほど洗練されていなかったのだ。
そんな些末な失敗をしている間にも、一日は終わりに近づいていた。
一応やらなければならないと思って試してみたのに、指があまりにも震えて出来なかった。今の自分ならば動揺の中でも変わらず出来るほど指先に芸が刷り込まれているけれど、当時は今ほど洗練されていなかったのだ。
そんな些末な失敗をしている間にも、一日は終わりに近づいていた。
確か、わたしは、すぐにマジックの練習を諦めて窓の外を見た。
なんでもない事だったけど、ジャージを着た男の人が走っていたのを見た。それは別に知り合いの誰かというわけではなかった。ただ、男性だった事だけは覚えている。
本当に、何でもない光景だった。
しかし、それを見て何を考えたかだけが、何となく今も記憶の中に張り付いていた。
なんでもない事だったけど、ジャージを着た男の人が走っていたのを見た。それは別に知り合いの誰かというわけではなかった。ただ、男性だった事だけは覚えている。
本当に、何でもない光景だった。
しかし、それを見て何を考えたかだけが、何となく今も記憶の中に張り付いていた。
あの人の視点の人生では、一体どんな波乱があったのだろう……という事だった。
わたしは、マジカラットという魔術団の孫(娘、でないのは、母が結婚を機に引退しているからだ)という特殊な境遇で生まれた。奇術には詳しく、いつかステージに立つ事を夢見ていたが、とても不器用だったので、どうも先が見えずに劣等感ばかり抱いていたのをよく覚えている。
ここまでも少し特殊だと思うが、本当に不思議なのはここからだ。
わたしは、聖杯戦争に巻き込まれる少し前には鏡の国からやって来た妖精に魔法を授けられ、『マジカルエミ』としてステージで不思議なマジックを披露していた事があるのだ。この日々もまた、聖杯戦争と同じくらい――あるいは聖杯戦争以上に貴重な時間だったけど、やはり遠い思い出の一つになってしまっている。
そして、この大勢が犠牲になった聖杯戦争で、わたしは生き残っていた。
自分の人生はこれまで、特別な事、不思議な事で満たされていた――。
だからこそ――果たして、それは本当に「特別」で「不思議」なのかがわからなかった。ああして走っているだけの人も、実は凄く変わった事や凄く不思議な事に溢れた人生を送っているかもしれないのだ。
わたしは、マジカラットという魔術団の孫(娘、でないのは、母が結婚を機に引退しているからだ)という特殊な境遇で生まれた。奇術には詳しく、いつかステージに立つ事を夢見ていたが、とても不器用だったので、どうも先が見えずに劣等感ばかり抱いていたのをよく覚えている。
ここまでも少し特殊だと思うが、本当に不思議なのはここからだ。
わたしは、聖杯戦争に巻き込まれる少し前には鏡の国からやって来た妖精に魔法を授けられ、『マジカルエミ』としてステージで不思議なマジックを披露していた事があるのだ。この日々もまた、聖杯戦争と同じくらい――あるいは聖杯戦争以上に貴重な時間だったけど、やはり遠い思い出の一つになってしまっている。
そして、この大勢が犠牲になった聖杯戦争で、わたしは生き残っていた。
自分の人生はこれまで、特別な事、不思議な事で満たされていた――。
だからこそ――果たして、それは本当に「特別」で「不思議」なのかがわからなかった。ああして走っているだけの人も、実は凄く変わった事や凄く不思議な事に溢れた人生を送っているかもしれないのだ。
たとえば、いま聖杯を破壊しに向かっている『ランサー』の東光太郎さんは、光の国から来た宇宙人と融合してウルトラマンタロウとして怪獣たちと戦ったらしい。
光太郎さんと一緒にいるはずのジョン・マクレーンさんは、アメリカで何度も何度も大きな事件に巻き込まれてきたと言う。
そのサーヴァントのアーチャー――ジョン・ランボーさんもまた、いくつもの戦場で生き残って来た人だ。
光太郎さんと一緒にいるはずのジョン・マクレーンさんは、アメリカで何度も何度も大きな事件に巻き込まれてきたと言う。
そのサーヴァントのアーチャー――ジョン・ランボーさんもまた、いくつもの戦場で生き残って来た人だ。
――そんな奇跡のような生き方を、本当は世界中の誰もがしているのではないかとわたしは窓辺で考えていた。
鏡の国から魔法を授かったのだって、本当はわたしだけではないのかもしれない。世界中の女の子が、普通の女の子のように見えて、実はそんな秘密を隠しているのかもしれないと思った。
だから、ああして、ただ走っているだけの人も、同じように不思議な秘密を抱えているのかもしれないと思った。
しかし、どんな人生を送っていても、こうして他人が窓から見る分には、ただのエキストラのようにしか見えないのだ……。もしかすると、それが一番の不思議なのではないかと、わたしはずっと思っていた。
それからわたしは、それを考える途方もなさに自然と飲まれて、すぐに飽きてしまい、もうそれ以上外を眺めるのをやめて、聖杯の事を考えた。
鏡の国から魔法を授かったのだって、本当はわたしだけではないのかもしれない。世界中の女の子が、普通の女の子のように見えて、実はそんな秘密を隠しているのかもしれないと思った。
だから、ああして、ただ走っているだけの人も、同じように不思議な秘密を抱えているのかもしれないと思った。
しかし、どんな人生を送っていても、こうして他人が窓から見る分には、ただのエキストラのようにしか見えないのだ……。もしかすると、それが一番の不思議なのではないかと、わたしはずっと思っていた。
それからわたしは、それを考える途方もなさに自然と飲まれて、すぐに飽きてしまい、もうそれ以上外を眺めるのをやめて、聖杯の事を考えた。
聖杯――それが今、光太郎さんたちの手で破壊されようとしているはずだった。
あるいは、もうされたのかもしれないと思っていた。
あるいは、もうされたのかもしれないと思っていた。
……そう思うと、ふと、わたしの中に、「それでいいのか?」という疑問は過った。
誰かの託した願いであったり、わたし自身の夢だったり、そういう物を叶える手法が一つ失われる結果になる。
壊してしまったものは決して直らないし、その器の破壊とともに、わたしの中の長いようで短い聖杯戦争は終わってしまうのだ。これまでの出会いもまた、聖杯がくれた物であるならば、聖杯を破壊する事はその否定のようにも思えた。
ずっと、聖杯の破壊ばかりを目的にしてきたが、もしかすると、それを無理に破壊する必要はどこにもないのではないかと思った。
誰かの託した願いであったり、わたし自身の夢だったり、そういう物を叶える手法が一つ失われる結果になる。
壊してしまったものは決して直らないし、その器の破壊とともに、わたしの中の長いようで短い聖杯戦争は終わってしまうのだ。これまでの出会いもまた、聖杯がくれた物であるならば、聖杯を破壊する事はその否定のようにも思えた。
ずっと、聖杯の破壊ばかりを目的にしてきたが、もしかすると、それを無理に破壊する必要はどこにもないのではないかと思った。
聖杯がある限り、聖杯戦争はこのまま永続するような気がした。
それは自分の命が脅かされない環境に置かれ、余裕を持った時だからの考えだったのだろう。しかし、突然に不安として胸をざわざわさせた。
そして、聖杯もまた時が壊していくのなら、わたしはその時の濁流をせき止めてみたいとさえ思ってしまった。聖杯戦争は悪い思い出ばかりな気もするが、余裕を持つと何かが終わる恐怖が強くなった。
けれど、わたしは部屋の中でそれを考えてみるだけで、結局、三人が聖杯を壊している事実をそっと空想しながら、じっと待っているだけだった。
時は長いようで、一瞬だった。
それは自分の命が脅かされない環境に置かれ、余裕を持った時だからの考えだったのだろう。しかし、突然に不安として胸をざわざわさせた。
そして、聖杯もまた時が壊していくのなら、わたしはその時の濁流をせき止めてみたいとさえ思ってしまった。聖杯戦争は悪い思い出ばかりな気もするが、余裕を持つと何かが終わる恐怖が強くなった。
けれど、わたしは部屋の中でそれを考えてみるだけで、結局、三人が聖杯を壊している事実をそっと空想しながら、じっと待っているだけだった。
時は長いようで、一瞬だった。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
聖杯戦争などという特殊環境に置かれながらも、あの夏休みがほんの一瞬の出来事のように感じたのは、それこそ、小学一年生の時と比べて一年がこんなに早いと気づいていたからだろう。いまこうして思い出しても、その点において、小学六年生が大人なのか子供なのかよくわからなくなってしまう。
時の流れは、徐々に早くなっていくのだ。
なんでも、八十歳まで生きたとしても、感覚的な折り返しは十代らしく、中学か高校を卒業した頃にはもう人生は折り返したような物であるらしい。
この時のわたしには、既に自分はこれからあと八倍の時間を生きるのだという実感は薄れていた。ただ、せいぜい、あと五倍はあるだろうという、微妙にわかり切れていないような考えだった。
時の流れは、徐々に早くなっていくのだ。
なんでも、八十歳まで生きたとしても、感覚的な折り返しは十代らしく、中学か高校を卒業した頃にはもう人生は折り返したような物であるらしい。
この時のわたしには、既に自分はこれからあと八倍の時間を生きるのだという実感は薄れていた。ただ、せいぜい、あと五倍はあるだろうという、微妙にわかり切れていないような考えだった。
だが、そんな人生の中でいくつもの不思議を経験し、わたしはきっと満たされていた。
それでも、その不思議にもいつしか終わりがやってきて、特別でもないごく普通の一人の人間に戻るのを、マジカルエミの時と、そしてこの聖杯戦争の時とでよく理解していた。
それでも、その不思議にもいつしか終わりがやってきて、特別でもないごく普通の一人の人間に戻るのを、マジカルエミの時と、そしてこの聖杯戦争の時とでよく理解していた。
わたしは、今日、小学校の夏休みが終わり、そして聖杯戦争が終わるのだという事に、ふと心を痛めて、午前中はそれからずっと泣いて過ごした。
なのに、午後にはけろっと忘れたように元気になって昼食を食べていた。
なのに、午後にはけろっと忘れたように元気になって昼食を食べていた。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
聖杯は、無事、三人の手で破壊されていた。
わたしの家を訪れたマクレーン刑事が、夕方ごろにそれを教えに来てくれた。マクレーンさんはぼろぼろで、おそらく聖杯を壊すという行為も大変な事だったのだろうと一目でわからせる姿だった。しかし、彼はやはり生きて帰って来た。
この時は、太陽は出ていたけど雨が降っていた。マクレーンさんは傘を差さなかったので、ぼろぼろな恰好の上にずぶ濡れという凄い状態だった。しかし、マクレーンさんは「いつもの事だ」と真顔で言った。茶化す風でもなかったので、威圧感さえ覚える言い方だったが、わたしは思わず笑った。
夕方に突然、晴れたまま雨が降り出した時に、わたしは洗濯物を混むのを手伝う事になったけど、それはちょうど聖杯が壊れた時と同じ頃の話だったらしい。「聖杯を壊してからちょうど雨が降った」というマクレーンさんの言葉で、わたしはそれが何時頃なのか知った。
そして、「やっぱり」と思った。
わたしの家を訪れたマクレーン刑事が、夕方ごろにそれを教えに来てくれた。マクレーンさんはぼろぼろで、おそらく聖杯を壊すという行為も大変な事だったのだろうと一目でわからせる姿だった。しかし、彼はやはり生きて帰って来た。
この時は、太陽は出ていたけど雨が降っていた。マクレーンさんは傘を差さなかったので、ぼろぼろな恰好の上にずぶ濡れという凄い状態だった。しかし、マクレーンさんは「いつもの事だ」と真顔で言った。茶化す風でもなかったので、威圧感さえ覚える言い方だったが、わたしは思わず笑った。
夕方に突然、晴れたまま雨が降り出した時に、わたしは洗濯物を混むのを手伝う事になったけど、それはちょうど聖杯が壊れた時と同じ頃の話だったらしい。「聖杯を壊してからちょうど雨が降った」というマクレーンさんの言葉で、わたしはそれが何時頃なのか知った。
そして、「やっぱり」と思った。
わたしは、この一時間ほど前に、聖杯は壊れて――そして、光太郎さんとランボーさんがいなくなったのを、洗濯物をこみながら悟っていたのだった。令呪が消滅して、体の負担がふと軽くなったのを、実際に感じていた。その時、わたしの動きはきっと、少し止まったような覚えがあった。
死とはまた違うだろうけど、わたしにとっては、知っている人と会えなくなる事は死と何ら変わらない話だった。
それはおそらく永遠のお別れだった。形あるものが崩れるように、目の前にいた人といつかお別れが来てしまう。
死とはまた違うだろうけど、わたしにとっては、知っている人と会えなくなる事は死と何ら変わらない話だった。
それはおそらく永遠のお別れだった。形あるものが崩れるように、目の前にいた人といつかお別れが来てしまう。
お礼もお別れも言う事が出来ずに、こうして永遠に引き裂かれてしまうのは、これで二度目だった。
わたしにとっては、わたしにマジカルエミの力を授けた妖精――『トポ』もまた、お別れの言葉一つ残せずに別れてしまった、たいせつな友人だった。今もわたしの机上には、トポが人間界に来ていた時に乗り移っていたモモンガのぬいぐるみが置いてある。こればかりはいつまでも捨てられなかった。動いて喋る事もなかったが、彼の持つ愛嬌を残していた。
わたしにとっては、わたしにマジカルエミの力を授けた妖精――『トポ』もまた、お別れの言葉一つ残せずに別れてしまった、たいせつな友人だった。今もわたしの机上には、トポが人間界に来ていた時に乗り移っていたモモンガのぬいぐるみが置いてある。こればかりはいつまでも捨てられなかった。動いて喋る事もなかったが、彼の持つ愛嬌を残していた。
わたしと別れたみんなに共通していたのは、みんな冷たい心の持ち主ではなかったという事だった。
しかし、やはり「最後」だとか「お別れ」だとか、そういう物は来る時に、そんな事は関係ないのだ。親しい者同士にもそっけないお別れが待っている事だって少なくない。
事実、お別れの時はどれだけ準備しようと思っても、全ての想いを言葉で表現しきれない。何か後悔が詰まって終わってしまう。
たとえ心のどこかで予期していても、お別れは常に唐突に感じてしまう事ばかりだった。わたしだけではなく、マクレーンさんもそう思っていたのかもしれない。どこか寂しそうに見えた。
しかし、やはり「最後」だとか「お別れ」だとか、そういう物は来る時に、そんな事は関係ないのだ。親しい者同士にもそっけないお別れが待っている事だって少なくない。
事実、お別れの時はどれだけ準備しようと思っても、全ての想いを言葉で表現しきれない。何か後悔が詰まって終わってしまう。
たとえ心のどこかで予期していても、お別れは常に唐突に感じてしまう事ばかりだった。わたしだけではなく、マクレーンさんもそう思っていたのかもしれない。どこか寂しそうに見えた。
それが、その日のわたしたちだった。
マクレーンさんも、本来は異世界で事件を解決していた刑事の方だったので、彼もすぐに元の世界に帰る事になるらしい。すると、おそらくもう会えなくなるのだろうと思った。
わたしにとって、お別れをする余裕があるのは、マクレーンさんくらいだった。
マクレーンさんも、本来は異世界で事件を解決していた刑事の方だったので、彼もすぐに元の世界に帰る事になるらしい。すると、おそらくもう会えなくなるのだろうと思った。
わたしにとって、お別れをする余裕があるのは、マクレーンさんくらいだった。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
それからしばらくして、空が暗くなった頃、空の上で花火が鳴った。聖杯戦争最後の陽も沈んでいき、あとはもう、八月一日より前の普通の日常に帰っていくというだけでしかなかった。
花火は大きく音を立てていたが、どこでお祭りをしていたのかはわからなかった。お祭りの話を今日の昼までにどこかで聞いたか見たかしたような気もしたが、わたしは近くのお祭りについては把握していなかった。ただ、折角なので、花火が見える角度から、空を見上げる事にした。
アスファルトからは乾いた土のような匂いと、雨の匂いがした。花火が水たまりで光るのは少し綺麗だった。
きっと、元々は雨が降った事で中止になりかけていたのだろう。空が暗くなるにつれ却って雨は止んでいったので、花火ができるようになったに違いない。
しかし、雨が降った事で却って、花火を綺麗に見せるギミックが一つ増えたように思えた。今もあの花火が印象に残っているのは、時折見下ろす事で花火を見ていたからだ。
花火は大きく音を立てていたが、どこでお祭りをしていたのかはわからなかった。お祭りの話を今日の昼までにどこかで聞いたか見たかしたような気もしたが、わたしは近くのお祭りについては把握していなかった。ただ、折角なので、花火が見える角度から、空を見上げる事にした。
アスファルトからは乾いた土のような匂いと、雨の匂いがした。花火が水たまりで光るのは少し綺麗だった。
きっと、元々は雨が降った事で中止になりかけていたのだろう。空が暗くなるにつれ却って雨は止んでいったので、花火ができるようになったに違いない。
しかし、雨が降った事で却って、花火を綺麗に見せるギミックが一つ増えたように思えた。今もあの花火が印象に残っているのは、時折見下ろす事で花火を見ていたからだ。
聖杯戦争を勝ち残った、ただ二人のマスターは、小川の走る小さなめがね橋の上に立ち、空を見上げたり、見下げたりしながら、それを見ていた。そこには何人もの人が、わたしたちを好奇の目で見つめるようにして通りすがっていた。
外国人の中年男性と、日本人の小学生の少女が、一体なぜ二人で花火を見ているのか……当時は気にしていなかったが、今思えば、それは、傍から見ればかなり異様な光景であったと思う。
誰かが推察しても、二人の関係性など真相はわからないだろうけど、わたしたちは二人でただ、空に打ちあがる大きな花火を眺めていた。
何も言う事なく、花火が一番綺麗に見えると思える場所で、わたしたちはそれを見ていた。
外国人の中年男性と、日本人の小学生の少女が、一体なぜ二人で花火を見ているのか……当時は気にしていなかったが、今思えば、それは、傍から見ればかなり異様な光景であったと思う。
誰かが推察しても、二人の関係性など真相はわからないだろうけど、わたしたちは二人でただ、空に打ちあがる大きな花火を眺めていた。
何も言う事なく、花火が一番綺麗に見えると思える場所で、わたしたちはそれを見ていた。
確かに花火はカラフルで綺麗だったが、わたしはやはり、どこかで不安に飲まれるようにしてそれを見ていた。
打ちあがっていく花火の速さに、何故か恐怖を感じて、それがはじけ飛んだ時に、取返しのつかない事が起きたような気持ちになってしまうのだった。
花火とは、時間をかけて作り上げた一つの玉が打ちあがって、壊れて空で爆ぜる催しだった。すると、玉は一つ、高速でこの世から消えてしまうという事になる。それが嫌だった。
花火が打ちあがるまでがあまりに速く、わたしの意識が負いきれないような速さで立つので――その音はわたしの心を急き立てていた。
打ちあがっていく花火の速さに、何故か恐怖を感じて、それがはじけ飛んだ時に、取返しのつかない事が起きたような気持ちになってしまうのだった。
花火とは、時間をかけて作り上げた一つの玉が打ちあがって、壊れて空で爆ぜる催しだった。すると、玉は一つ、高速でこの世から消えてしまうという事になる。それが嫌だった。
花火が打ちあがるまでがあまりに速く、わたしの意識が負いきれないような速さで立つので――その音はわたしの心を急き立てていた。
そして、この花火が終わりの合図であるのも、わたしはわかっていた。
一つ一つの花火が、一つの時間を終える区切りになっているのをわたしは感じていた。
遠くから聞こえる祭りの太鼓の音もまた、わたしの気持ちを煽り続けた。
太鼓の音も、花火の音も、普段の生活の中では絶対にありえない音で、わたしは別にその祭りに参加しているわけでもないのに、祭りの後の寂しさを少し感じていた。
一つ一つの花火が、一つの時間を終える区切りになっているのをわたしは感じていた。
遠くから聞こえる祭りの太鼓の音もまた、わたしの気持ちを煽り続けた。
太鼓の音も、花火の音も、普段の生活の中では絶対にありえない音で、わたしは別にその祭りに参加しているわけでもないのに、祭りの後の寂しさを少し感じていた。
そう。
それは、「小学校六年生の夏休み」の終わりであり、「聖杯戦争」の終わりであり、「少女」の終わりであった。
ふと見れば、マクレーンさんはどこか――きっと元の世界に、消えていた。そして、わたしはそれから先――それは、今日まで、マクレーンさんに会う事はなかった。
それは、「小学校六年生の夏休み」の終わりであり、「聖杯戦争」の終わりであり、「少女」の終わりであった。
ふと見れば、マクレーンさんはどこか――きっと元の世界に、消えていた。そして、わたしはそれから先――それは、今日まで、マクレーンさんに会う事はなかった。
わたしは、最後まで花火を眺め続けるのが怖くなったが、それでもその場から離れたくなくて、ひたすら花火を目で追い、心の中で焦り続けていた。胸がひたすら跳ね続け、それは泣いている時と同じようなリズムで動いていた。
そして、気づけば本当に、目から涙が溢れていた。迷子になったかのように泣き続けるわたしに、大人たちは声をかけたが、理由を問われても、わたし自身は答える事が出来なかった。
そして、気づけば本当に、目から涙が溢れていた。迷子になったかのように泣き続けるわたしに、大人たちは声をかけたが、理由を問われても、わたし自身は答える事が出来なかった。
そして、そんな中で、わたしは小さな戦争の終わりを感じていた。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
聖杯戦争。
……それは、少女期にわたしが出会った、不思議な体験であり、大切な思い出の一つだった。
子供の頃の部屋で、ただ明け方の窓を眺める二十二歳のわたしにとっては、幼い日の妄想のようにも思えるような過去である。
どれだけアルバムを眺めても、あの時の思い出だけは振り返る事が出来ないし、客観的にあの出来事証明できる方法なんてない。
本当に、わたしの記憶の中にしかない話なのかもしれない。
……それは、少女期にわたしが出会った、不思議な体験であり、大切な思い出の一つだった。
子供の頃の部屋で、ただ明け方の窓を眺める二十二歳のわたしにとっては、幼い日の妄想のようにも思えるような過去である。
どれだけアルバムを眺めても、あの時の思い出だけは振り返る事が出来ないし、客観的にあの出来事証明できる方法なんてない。
本当に、わたしの記憶の中にしかない話なのかもしれない。
あの時撮った写真があった気がするけど、それは、いつの間にかみつけられなくなってしまった。写真そのものが泡のように消えてしまったのかもしれない。
マジカルエミの存在が時代の中で人々から忘れられたように、聖杯戦争の思い出も時が進むにつれ香月舞の胸の中から少しずつ消えていくようになったのだ。
マジカルエミの存在が時代の中で人々から忘れられたように、聖杯戦争の思い出も時が進むにつれ香月舞の胸の中から少しずつ消えていくようになったのだ。
わたしは、たまに夜中の二時まで起きていて、ふとあの時の事を思い出して胸がいっぱいになったりもする。
そして衝動的に、ほら、こんな風にアルバムを取り出してめくってみたりする。
そして衝動的に、ほら、こんな風にアルバムを取り出してめくってみたりする。
……だけど、いつかあったはずの写真は、もう、アルバムの空白になっていた。
まだ若い頃の両親や祖父母が、幼い舞を想って挟んだ写真たちに並べて、そっと挟んだはずの写真は――どこにあるのかわからない。
しかし、それを悲しいと思わなかった。
失くす瞬間には悲しみが湧き出ても、とうに失くしていた事実に対しては妙に割り切れてしまうのが、人間という生き物だった。
だが、遠い日の出来事だと思って、どうでもよくなってしまっているのかもしれないと思うと、それは流石に悲しかった。それでも、少なくとも、そういうわけではないと思いたかった。
まだ若い頃の両親や祖父母が、幼い舞を想って挟んだ写真たちに並べて、そっと挟んだはずの写真は――どこにあるのかわからない。
しかし、それを悲しいと思わなかった。
失くす瞬間には悲しみが湧き出ても、とうに失くしていた事実に対しては妙に割り切れてしまうのが、人間という生き物だった。
だが、遠い日の出来事だと思って、どうでもよくなってしまっているのかもしれないと思うと、それは流石に悲しかった。それでも、少なくとも、そういうわけではないと思いたかった。
いつの間にか、淡い思い出は輪郭がわからなくなってきていた。
あの時出会った光太郎さんの顔も思い出せないし、外国人を見るとマクレーンさんに似ているような気がして振り返ってしまうような事がある。
ランボーさんだけは、あれから何度か映画の中で目にする事になったけれど、そこにいるのは一人の俳優でしか無かった。彼はわたしの事を知らないし、わたしが見ている彼も全く別の概念だった。
ただ、リバイバル上映を見に行った時に見た彼の姿は、やはり舞が見てきた通りの果敢さであった。ヘリを弓矢で撃ち落とすシーンなど、実際に見た時の迫力と何ら変わらないと思えるほどだった。
あれから何度も時を重ね、いつの間にか、聖杯戦争の一週間は、そんな映画の中の光景に塗り替えられるようになった。
あの時出会った光太郎さんの顔も思い出せないし、外国人を見るとマクレーンさんに似ているような気がして振り返ってしまうような事がある。
ランボーさんだけは、あれから何度か映画の中で目にする事になったけれど、そこにいるのは一人の俳優でしか無かった。彼はわたしの事を知らないし、わたしが見ている彼も全く別の概念だった。
ただ、リバイバル上映を見に行った時に見た彼の姿は、やはり舞が見てきた通りの果敢さであった。ヘリを弓矢で撃ち落とすシーンなど、実際に見た時の迫力と何ら変わらないと思えるほどだった。
あれから何度も時を重ね、いつの間にか、聖杯戦争の一週間は、そんな映画の中の光景に塗り替えられるようになった。
だが、時がどれだけ過ぎて、思い出が淡く消え去りそうになっても、やはりわたしにとっては、あの聖杯戦争の記憶は特別な物に違いなかった。こうして……ひとりアルバムをめくって、その空白を覗いた時だけは、わたしも小六の夏を感じる事が出来るのだ。
微かに体のどこかを過る、あの時のリアルと、あの時の感情の再現が、今もそっと胸を締め付けてくれる。それもまたすぐに消えてしまうが、また忘れた頃に記憶を掘り返すと、同じような感覚が胸を走る。
無邪気の時を追想する楽しみに、ほんの一瞬だけ耽る事ができるのだ。それが時に、何故か無性に楽しく思えた。
微かに体のどこかを過る、あの時のリアルと、あの時の感情の再現が、今もそっと胸を締め付けてくれる。それもまたすぐに消えてしまうが、また忘れた頃に記憶を掘り返すと、同じような感覚が胸を走る。
無邪気の時を追想する楽しみに、ほんの一瞬だけ耽る事ができるのだ。それが時に、何故か無性に楽しく思えた。
その一瞬――現実と現実の間にそっとできる空白が、今のわたしにとって感じられる『聖杯戦争』だった。
あの時と比べて、随分と思い出は小さく、見えづらくなってしまったかもしれないが、しかし、悩んだ時に何となく、わたしの生きてきたこれまでを、そしてこれから生きる意味を教えてくれる――そんな、小さなコンパスの針でもあった。
あの時と比べて、随分と思い出は小さく、見えづらくなってしまったかもしれないが、しかし、悩んだ時に何となく、わたしの生きてきたこれまでを、そしてこれから生きる意味を教えてくれる――そんな、小さなコンパスの針でもあった。
揺れるカーテンの向こうで、電車の踏切の音が小さく鳴り始めた。
わたしは、その音を見つめるように、あの時と比べて少しだけ変わったような街並みに目をやり、微笑んだ。
また、二度と来る事のない昨日が終わり、新しい一日が始まろうとしている。
わたしは、その音を見つめるように、あの時と比べて少しだけ変わったような街並みに目をやり、微笑んだ。
また、二度と来る事のない昨日が終わり、新しい一日が始まろうとしている。
【空白のなかの聖杯戦争 完】
使用候補作品
(ただし一部設定が変更されており、厳密にはここからの続編というわけではありません)